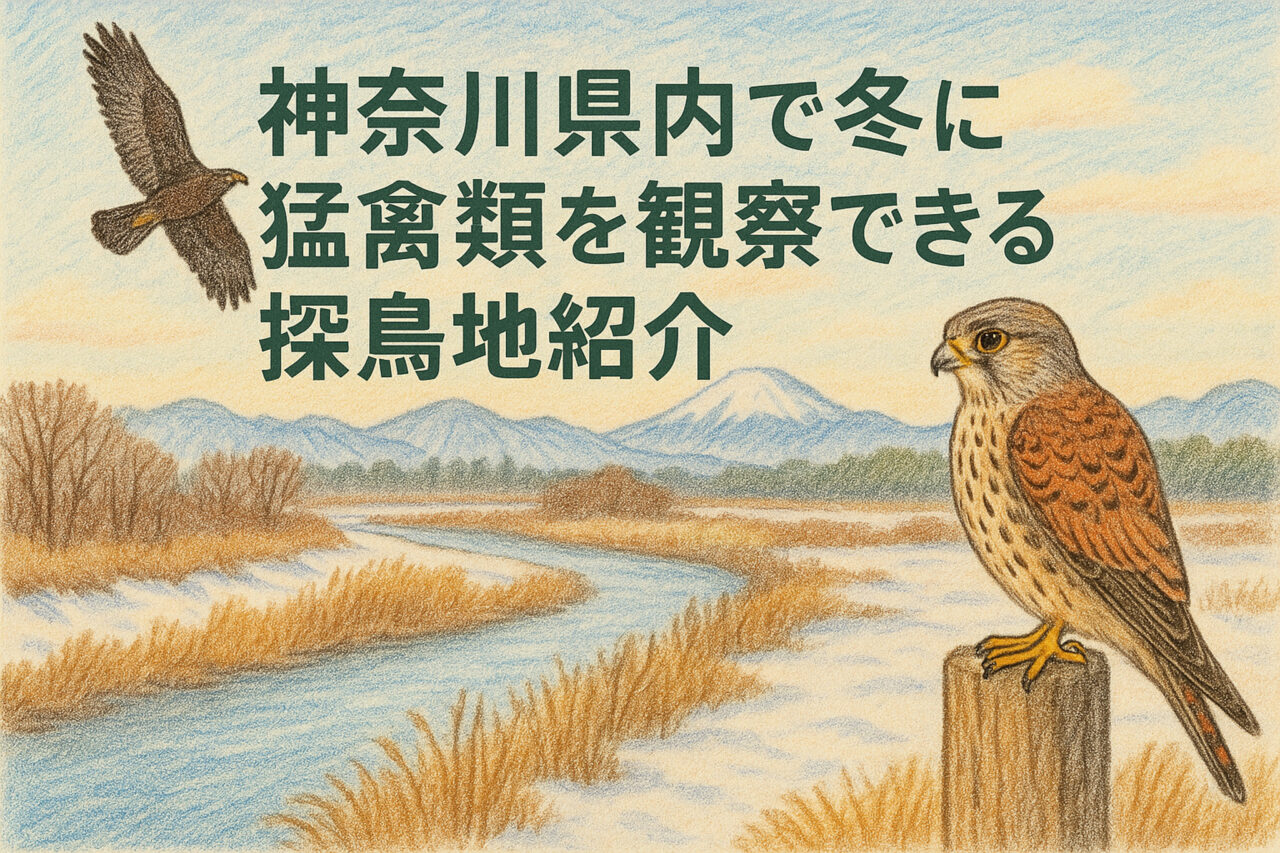
はじめに
神奈川県内には冬の時期に猛禽類を観察できる探鳥地・観察スポットが各地に点在しています。東京湾や相模湾に面した海岸や河川敷、里山の谷戸や都市公園など、多彩な環境が揃っており、それぞれで出会える猛禽類の種類や楽しみ方も様々です。たとえば海沿いではミサゴやハヤブサ、内陸の河川敷や公園ではノスリやチョウゲンボウ、ハイタカなどが観察対象になります。冬は多くの野鳥が渡来し猛禽類の観察好機となる季節ですので、バードウォッチング初心者の方もぜひ寒さ対策を万全にしてフィールドに出かけてみましょう。
本記事では神奈川県内で冬に猛禽類が観察できる探鳥地をできるだけ多く紹介します。それぞれアクセスしやすく初心者にも比較的観察しやすい場所ばかりです。各スポットごとの主な環境や見られる猛禽類、観察のポイントなどを解説しますので、冬のバードウォッチング計画の参考にしてください。
多摩川河口付近〖川崎市〗

多摩川が東京湾に注ぐ河口の神奈川県側エリアは、冬に猛禽類を観察したい初心者に特におすすめの探鳥地ですこの場所はミサゴの観察スポットとして非常に有名で、冬の週末になると多くのバードウォッチャーや野鳥写真家が集まります。河口近くの川中には漁業の杭が点在しており、魚を捕えたミサゴがしばしば止まって休むため必ずチェックしましょう。南岸にあたる神奈川側の堤防上から観察すれば日中は順光となり、運が良ければ飛翔するミサゴを自分の目線より低い位置で見下ろすこともできます。
近年、この多摩川河口ではかつてよく見られたチョウゲンボウ(小型のハヤブサ科猛禽)の姿が減ってきています。以前は河川敷の草地でホバリングしながら狩りをする姿が観察できましたが、その狩場となる草地が開発で次々失われた影響で、今後チョウゲンボウの観察機会は少なくなると考えられています。ミサゴの豪快なダイビングや獲物を掴んで飛ぶ姿を堪能しつつ、周辺の電柱や空にも目を配り、タイミングが合えばチョウゲンボウや上空を舞うトビ(トビは留鳥)が見られるかもしれません。広い河口エリアなので双眼鏡やフィールドスコープがあるとより探しやすいでしょう。
二ヶ領宿河原堰〖川崎市〗

多摩川中流部に位置する二ヶ領宿河原堰(にかりょうしゅくがわらぜき)は、東京都側・神奈川県側双方から観察できる探鳥地ですが、神奈川県川崎市側は登戸駅から徒歩圏内でアクセスが良く、昼間は順光で野鳥が観察しやすいポイントです。冬になると堰周辺にはヒドリガモやコガモ、マガモにオカヨシガモなど多数のカモ類が飛来し、視界を遮るものもないため水鳥観察には絶好の環境が広がります。様々な種類のカモが集まるので識別の練習にも適しており、バードウォッチング初心者がスコープ越しにカモ類の見分けを学ぶ場としてもおすすめです。
猛禽類ではミサゴが秋から冬にかけて頻繁に姿を現します。秋には狩りをするミサゴのダイナミックなシーンが観察できることがあり、冬でも広範囲を飛び回って魚を狙うミサゴを堰周辺で目にする機会があります。ミサゴは二ヶ領宿河原堰を中心に上流下流へと行動範囲が広いため、水面を広く見渡せる堰下の柵沿いなどで待ち構えてみましょう。運が良ければ頭上を飛ぶミサゴを間近に捉えることもできます。そのほか、堰の周辺では冬にトビが上空を旋回する姿も見られるほか、川原の草地にはタヒバリなど小鳥類も生息しており、猛禽類の出現を察知して一斉に飛び立つ様子が見られることがあります。
寒川取水堰〖高座郡寒川町〗

相模川の下流域にある寒川取水堰(さむかわしゅすいぜき)は、冬に多くの野鳥が集まることで知られる神奈川県内屈指の探鳥地です。越冬の水鳥が相模川に数多く飛来し、河川敷にはホオジロやヒバリ、カシラダカなどの小鳥類も姿を見せます。それら水鳥や小鳥を狙って現れる猛禽類も多く、寒川取水堰周辺では冬にチョウゲンボウ、トビ、ノスリ、ハイタカといった猛禽類が観察されます。特に土手の上から広い河川敷全体を見渡していると、高い確率で上空を飛ぶ猛禽類の姿を捉えられるでしょう。猛禽が出現すると、周囲にいたカモ類など水鳥が一斉に飛び立つため、その動きで猛禽類の存在に気付くこともあります。
寒川取水堰では堰本体や周辺の水面に水鳥が多いため、猛禽類はしばしば川沿いの樹木や鉄塔などに留まります。実際、堰の東側を通る高速道路沿いの鉄塔にノスリやチョウゲンボウが止まっているのが観察されることがあり、高倍率の双眼鏡やスコープがあればチェックしてみましょう。土手を歩きながら周囲の開けた場所、高い構造物の上や対岸の林の上空などをくまなく探すのがコツです。また、駅から徒歩圏内なのも魅力で、JR相模線・宮山駅から15分ほど歩けば河川敷に出られます。アクセスの良さも手伝って冬場は探鳥者が多い人気スポットなので、譲り合って観察し、マナーを守って楽しみましょう。
相模大堰〖厚木市・海老名市〗

相模川中流にある相模大堰(さがみおおぜき)は、年間を通じて野鳥観察者に親しまれている探鳥地ですが、特に冬は水鳥と猛禽類の両方が期待できるスポットです。JR相模線・社家駅から徒歩5分ほどで着けるアクセスの良さもあり、初心者が気軽に訪れてバードウォッチングを楽しむのに適しています。堰には管理橋が架かっており歩行者も渡れるため、川の両岸から広く相模川を見渡すことができます。
冬の相模大堰周辺では、カモ類やカンムリカイツブリ、オオバンなど多くの水鳥が越冬のため集まります。そして水辺にはミサゴの姿も見られます。相模大堰のすぐ上流は開けた空間になっており、上空を飛ぶミサゴを観察しやすいポイントです。ミサゴが獲物を探して川面上空を旋回する様子や、ダイブして魚を捕獲するシーンが目撃できることもあります。運が良ければ堰のコンクリートブロック上で休むミサゴを発見できるかもしれません。なお、相模大堰はヨシガモやヒドリガモなど珍しいカモ類が見られる場所としても知られ、なかでもカワアイサは特筆すべき冬の主役です。カワアイサの群れが相模川に飛来し盛んに潜水を繰り返す様子は遠目からでも確認できます。ぜひ管理橋を移動しつつ順光になる位置から、水鳥とともに猛禽類の動きも探してみましょう。
相模川河口〖平塚市・茅ヶ崎市〗

相模川が相模湾に注ぐ河口一帯も、冬に猛禽類を含む様々な野鳥が観察できるエリアです。周辺は湘南地域の砂浜海岸や広い河川敷があり、視界を遮るものが少ないため初心者でも野鳥を見つけやすいでしょう。特に冬はヒドリガモ、コガモ、オカヨシガモといったカモ類やカンムリカイツブリが多数飛来し、川岸の堤防の上から双眼鏡で広範囲を探せば水面に浮かぶ水鳥の群れを見つけることができます。それらのカモ類の上空にはミサゴが魚を狙って飛来することがあります。実際、相模川河口では冬場にミサゴが姿を見せることが知られており、上空を注意深くチェックしていれば大きな猛禽類が旋回しているのを発見できるでしょう。ミサゴは魚を捕らえると近くの陸地へ運んでいく習性があるため、捕えた魚を掴んで飛ぶ姿に出会える可能性もあります。
河口周辺ではトビも日常的に見られます。トビは神奈川県内では留鳥として一年中どこでも目にすることができる身近な猛禽ですが、ここ相模川河口でも例外ではありません。海風に乗って上昇気流を捉えながら優雅に旋回する姿は初心者にも見つけやすく、まずはトビを探して双眼鏡で追う練習をしてみるのも良いでしょう。なお、相模川河口の東側(茅ヶ崎市側)には草地と防風林が広がっており、冬にはジョウビタキなどの小鳥も見られます。海岸線にはユリカモメやウミウなども飛来するためフィールドは賑やかです。広範囲を見渡しつつ猛禽類の動きに注目してみてください。
酒匂川河口〖小田原市〗

神奈川県西部、小田原市を流れる酒匂川(さかわがわ)の河口周辺も一年を通して野鳥が多いエリアで、冬には猛禽類の姿も期待できます。酒匂川では主に西側(小田原市側)の河川敷が観察ポイントとなっており、午後には日差しが順光になるため冬場でも快適に探鳥ができます。川沿いの道は見通しが良く、初心者でも野鳥を見つけやすい環境です。冬の酒匂川河口ではカモ類やカンムリカイツブリ、ハマシギの大群、ユリカモメなど水辺の鳥が大変豊富で、日によっては無数の野鳥が水際を埋め尽くす光景に出会えるでしょう。
猛禽類ではミサゴに注目です。酒匂川の河口付近では冬にミサゴが飛来することがあり、上空をよく確認すると悠々と旋回する姿を発見できます。ミサゴは海と川の境界で魚を狙って飛来するため、川の河口から相模湾の方向にかけて目を凝らしてみましょう。運が良ければ水面に急降下して魚を捕まえる瞬間を観察できるかもしれません。さらに、酒匂川流域はカワアイサの飛来地としても有名です。猛禽ではありませんが、冬だけ見られる大型カモの一種で真っ白なオスの姿が美しく、一見の価値があります。カワアイサは河口から少し遡った飯泉取水堰付近や鉄道橋周辺でよく観察されています。こうした水鳥の動きにも注意を払いながら、上空の猛禽類を探してみてください。酒匂川河口へはJR東海道線・鴨宮駅から徒歩15分程度で河川敷に出られます。
観音崎公園〖横須賀市〗

東京湾に面した三浦半島東端の観音崎公園は、海岸から林まで多様な環境で野鳥観察が楽しめるスポットです。冬になると海岸沿いにはウミウやヒメウなど海鳥が姿を現し、園内の斜面林にはシロハラやルリビタキといった冬鳥が飛び交います。猛禽類も例外ではなく、トビは通年見られるほか、冬季にはノスリやハイタカが上空に飛来する姿が観察されています。開けた海の見晴らし台や展望園地など広範囲を見渡せるポイントから空を見上げてみましょう。冬晴れの日には、青空をバックにタカが旋回する雄大なシーンに出会えるかもしれません。
また、観音崎公園ではハヤブサが見られることでも知られています。海岸の崖沿いに広がる斜面林では、冬にハヤブサやノスリなど猛禽類が木々や岩場に止まっていることがあるため要チェックです。実際、崖に生えた木の枝や岩棚に留まるハヤブサの姿が確認されており、運が良ければ高速で飛翔し獲物を狙うハヤブサの狩りの瞬間に遭遇できるでしょう。観音崎公園内の遊歩道は起伏がありますが、灯台周辺の高台から海と空を一望できるため猛禽探しには最適です。なお、公園付近には磯遊びや釣り人も多いため、野鳥が驚かないよう人の少ない時間帯(早朝など)に訪れるのがおすすめです。
城ヶ島〖三浦市〗

三浦半島の南端に位置する城ヶ島は、周囲を海に囲まれた磯と断崖の探鳥地です。冬はウミウやヒメウが越冬のため多数飛来し、島内の各所から海鳥の観察が楽しめます。猛禽類の観察という点では、島の東側にあるウミウ展望台が一つのポイントになります。ここから対岸の崖を望むと、群れで休むウミウの中に混じって時折ハヤブサが姿を見せます。崖にとまるハヤブサを双眼鏡やスコープで探すときは、ウミウの群れから少し離れた場所に注目してみると良いでしょう。灰色がかった体で岩肌に溶け込みやすいハヤブサですが、動き出せば鳩ほどの大きさながら猛禽ならではの鋭い飛翔で存在感を放ちます。
城ヶ島ではミサゴも冬の時期に周辺海域で見られることがあります。島全体が海に囲まれているため、獲物を狙うミサゴが沖合から飛来し島の岩礁にとまる姿や、上空を旋回する姿が観察されます。特に波静かな日には海面上にホバリングした後ダイブして魚を捕らえるシーンに出会える可能性もあります。その他、島内ではトビが常時見られ、磯ではクロサギやイソヒヨドリなども観察対象になります。足場が悪い岩場も多いので安全に注意しつつ、海風の中で猛禽類を探す醍醐味を味わってみてください。
新横浜公園〖横浜市〗

横浜市にある新横浜公園は、都心近くで冬鳥の観察が楽しめる都市公園型の探鳥地です。園内北側に広がる大池には冬になると多数のカモ類が飛来し、特にミコアイサの人気が高く多くのバードウォッチャーが訪れます。水鳥が豊富なため猛禽類も姿を見せることがあり、ノスリなどが大池上空や隣接する鶴見川の上空を飛ぶのが観察されることがあります。冬に新横浜公園を訪れた際は、水面だけでなくときおり空も見上げて猛禽類の飛翔がないかチェックしてみましょう。上空を旋回するノスリのシルエットはカモ類とは全く異なる大きな翼ですぐに判別できます。
新横浜公園はアクセスが良く、JR横浜線・小机駅から徒歩5分ほどで公園入口に到着します。園内も整備され歩きやすいため、双眼鏡片手に散策しながら野鳥観察するにはもってこいです。大池の周囲には観察デッキや柵沿いの観察ポイントがあり、初心者でも野鳥との距離を詰めて観察できるでしょう。水辺にはカワセミも生息しており、一緒に探してみるのも楽しいです。冬晴れの日には青空をバックにノスリが舞う姿と、池で遊ぶミコアイサなどを同時に楽しめるかもしれません。都市公園とは思えない充実した探鳥体験ができるでしょう。
座間谷戸山公園〖座間市〗

座間谷戸山公園は、神奈川県内陸部の座間市に位置し、里山の谷戸(細長い谷間)地形を活かした自然豊かな都市公園です。冬にはジョウビタキやシロハラ、ツグミなど多くの冬鳥が訪れることで知られ、バードウォッチング初心者にも人気の探鳥地となっています。園内には林と草原、水辺が一通り揃っており、多様な野鳥が観察できます。ハイタカをはじめとする猛禽類も例外ではなく、運が良ければ森林の水場で水浴びをするハイタカの姿を観察できることがあります。実際、公園内の「水鳥の池」では浅瀬に設置された野鳥観察小屋の近くでハイタカが水浴びしていた記録もあり、デッキから池の杭や水際の枝をよくチェックすると良いでしょう。
座間谷戸山公園では他にもチョウゲンボウなど小型の猛禽類が見られることがあります。上空高くチョウゲンボウがホバリングして獲物を探していることもあります。人の多い日中は野鳥たちも警戒心を強めますので、可能であれば比較的人の少ない午前中の早い時間帯や夕方に訪れると観察しやすいでしょう。園路が狭い箇所もあるため、三脚使用時は通行の妨げにならないよう配慮してください。最寄りの小田急線・座間駅から徒歩10分ほどでアクセスでき、駐車場も整備されています。初心者の練習の場としても適した里山公園です。
まとめ
神奈川県内には以上のように冬の猛禽類観察に適した探鳥地が数多く存在し、海岸・河川敷・森林・公園といった異なる環境ごとに多彩な魅力があります。それぞれのフィールドによって出会える猛禽類の種類も変化し、季節ごとの見どころも様々です。観察に出かける際は野鳥および地元の方々への配慮を忘れないようにしましょう。特に農耕地や河川敷では農作業や釣り人の邪魔にならないよう細心の注意を払い、越冬中や繁殖期の野鳥にはむやみに近づかず静かに観察することがバードウォッチングの基本マナーです。また、防寒対策を万全にするとともに、海岸部では風よけも準備しておくと安心です。遠くの猛禽類まで視界に捉えるには双眼鏡やフィールドスコープがあると便利ですので、ぜひ持参しましょう。ルールとマナーを守り十分な準備をしてフィールドに出れば、神奈川県ならではの冬の猛禽類観察を存分に楽しめるはずです。バードウォッチング初心者の方も、ぜひ冬ならではの猛禽との出会いを満喫してください。


コメント