
北海道の冬を代表する鳥といえば「シマエナガ」。
そのふわふわした真っ白な姿とつぶらな瞳から「雪の妖精」とも呼ばれ、近年ではSNSやテレビでも大人気の野鳥です。
この記事では、シマエナガの特徴や見られる場所、鳴き声の聞き分け、撮影のコツなどを、バードウォッチング初心者にもわかりやすく解説します。
シマエナガとは?その魅力と名前の由来
シマエナガ(学名:Aegithalos caudatus japonicus)は、エナガという鳥の亜種で、北海道のみに生息する小鳥です。(過去に本州での観察例もあり)
全長はわずか13〜14cm、体重は7〜9g程度。日本の野鳥の中でも特に小さく、まるで雪の中のぬいぐるみのような存在です。
「雪の妖精」と呼ばれる理由
その理由は、なんといっても真っ白な顔とふっくらした体。
他地域に生息する本州のエナガは、顔に黒い過眼線(アイライン)があり、少し精悍な印象ですが、シマエナガにはそれがなく、全体が白い顔に見えるのが特徴です。
このため、雪の中でまるで妖精のように浮かび上がる姿が「雪の妖精」と呼ばれるようになりました。

シマエナガの特徴:小さくて愛らしい体のしくみ
シマエナガは、丸い体と長い尾羽を持つ小鳥です。
「エナガ」の名前は、文字通り「柄(尾)」が長いことに由来しています。
体の半分ほどが尾羽という独特のバランスで、止まり木にちょこんと座る姿は思わず見惚れてしまうほど。
羽毛のふくらみ
冬のシマエナガは体をふくらませて熱を逃さないようにしています。
そのため、写真や肉眼で見ると「まるで綿菓子のよう」に見えることがあります。
羽毛の密度が高く、防寒性能が非常に優れています。
目とくちばし
つぶらな黒い瞳と短いくちばしもチャームポイント。
雪景色の中では、目とくちばしの黒が白い体とのコントラストを作り、独特の存在感を放ちます。
北海道でシマエナガに出会える場所と時期
シマエナガは北海道全域に分布していますが、地域や季節によって観察しやすさが変わります。
ベストシーズン:冬(12月〜3月)
冬になると、森の奥から平地や公園にも下りてきます。
寒さで群れを作るようになるため、複数羽で枝から枝へ飛び回る姿を見られる確率が高くなります。
この季節は葉が落ちて見通しも良く、観察・撮影の絶好期です。
初心者におすすめの観察スポット
- 札幌エリア:円山公園、藻岩山、滝野すずらん丘陵公園
- 旭川エリア:北邦野草園、就実の丘
- 帯広・釧路方面:音更町の公園、釧路湿原周辺
- 函館エリア:香雪園(見晴公園)や亀田八幡宮周辺
これらの場所では、冬場にエゾリスやハシブトガラなど他の小鳥と一緒に観察できることもあります。
「小鳥の混群」に出会えたら、その中にシマエナガがいる可能性は高いです。
鳴き声で見つける:シマエナガの音の特徴
シマエナガは見た目だけでなく、鳴き声も非常に可愛らしい鳥です。
高く澄んだ声で「ジュルルル」「チーチー」「ツリリリ」などと鳴き、群れ同士でコミュニケーションを取っています。

鳴き声
特に冬は、木々の間から「ジュルルル」という声が響くことが多く、それがシマエナガ発見のサインになります。
双眼鏡を向ける前に、まず耳を澄ますのがポイントです。
シマエナガの生態:群れで生きる小さな命
群れ行動の理由
シマエナガは冬になると10〜20羽ほどの群れを作ります。
これは、体温を保ち、効率的に餌を探すための戦略です。
1羽で生きるには寒さが厳しすぎるため、互いに鳴き声で連絡を取り合いながら移動します。
食べ物
主食は昆虫やクモ、小さな木の実。
冬は樹皮の間に潜む虫を見つけ出すなど、驚くほど器用です。
また、春には繁殖期を迎え、巣作りに忙しくなります。
巣作り
シマエナガの巣は、コケやクモの糸を使って作られた球状の巣。
まるで手芸品のような緻密な構造で、出入り口が小さく、外敵から卵を守ります。

SNSで人気爆発!「日本一かわいい鳥」と呼ばれる理由
SNSでは「#シマエナガ」「#雪の妖精」などのハッシュタグで多くの写真が投稿されています。
特にInstagramやX(旧Twitter)では、ふわふわの姿が人気を呼び、「日本一かわいい鳥」と評されるようになりました。
観光地ではシマエナガグッズも増加しており、マグカップ、ぬいぐるみ、手帳なども人気。
北海道のシンボル的存在として、観光キャンペーンに登場することもあります。

撮影のコツ:ふわふわ感と雪景色を美しく撮る方法
カメラ設定の基本
- レンズ:焦点距離200mm以上の望遠レンズ
- シャッタースピード:1/1000秒以上(素早い動きに対応)
- 露出補正:+0.3〜1.0(雪の反射により暗く写りがちなため)
- 連写モード:必須。枝から枝へ動く瞬間を狙う
光の使い方
朝や夕方の柔らかい光を利用すると、羽毛の立体感が出やすくなります。
曇りの日は白飛びしにくく、ふわふわした質感を捉えやすいです。
マナー
近づきすぎると逃げてしまうため、望遠レンズで距離を保つことが大切。
また、鳴き声を真似たり餌付けをするのは控えましょう。
四季で変わるシマエナガの姿
| 季節 | 行動 | 観察のポイント |
|---|---|---|
| 春(4〜6月) | 巣作り・繁殖 | ペアで行動することが多い |
| 夏(7〜8月) | 高山帯へ移動 | 涼しい森の奥に生息 |
| 秋(9〜11月) | 群れ形成 | 冬に向けて再び集団行動 |
| 冬(12〜3月) | 平地へ | 最も観察しやすい時期 |

シマエナガ観察のマナーと注意点
観察・撮影を楽しむうえで、野鳥を驚かせたりストレスを与えないことが最も大切です。
- 巣やヒナを探す行為は絶対にしない
- 鳴き声や餌で誘引しない
- 撮影時のフラッシュを使わない
- 鳥の通り道に立ち入らない
- ゴミを残さず、自然をそのままに
よくある質問(FAQ)
Q1. シマエナガは北海道のどこでも見られますか?
→ 基本的には全道に分布しますが、特に道央・道東で観察しやすいです。
Q2. 鳴き声はいつ聞けますか?
→ 冬でも鳴きますが、繁殖期(春)にはさらに多様な声を発します。
Q3. 飼うことはできますか?
→ 野鳥保護法により、捕獲や飼育は禁止されています。観察だけを楽しみましょう。
まとめ:北海道の冬を彩る「雪の妖精」に会いに行こう
白い雪原の中を軽やかに舞うシマエナガ。
その姿を一目見れば、誰もが心を奪われます。
寒い冬の日、静かな森で「ジュルルル」という小さな声を聞いたら、近くに雪の妖精がいるかもしれません。
観察マナーを守りながら、北海道の自然とともにこの小さな命を見守っていきましょう。


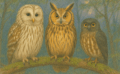
コメント