
冬は木々の葉が落ちて視界が開け、水辺のカモ類(カモ科の水鳥)の観察に最適な季節です。神奈川県内にも、冬になると多くのカモ類が集まる探鳥地が各地に点在しています。本記事ではバードウォッチング初心者の方向けに、カモ類とはどんな野鳥か、冬に見られる主なカモの種類、そして神奈川県内のおすすめカモ観察スポットをわかりやすく紹介します。さらに、冬季におけるカモ観察のコツや注意点、初心者が揃えておきたい持ち物・服装のアドバイスについても解説します。冬の神奈川でカモ類の魅力を存分に楽しむためのガイドとしてぜひご活用ください。
カモ類とはどんな鳥?初心者向けに解説
カモ類(カモ科)とは、ガン(雁)やハクチョウ(白鳥)の仲間に分類される水鳥のグループです。一般的に「カモ」と呼ぶ場合、川や湖、池などの水辺で見られる中型の水鳥を指し、マガモやカルガモなどが代表的です。平たいくちばしと水かきのついた脚を持ち、水面を泳いだり水中に潜ったりして植物の葉・種子や小魚、水生昆虫などを食べます。日本では多くのカモ類が冬鳥(冬にシベリアなどから渡来して越冬する渡り鳥)で、秋に飛来して春先に北へ帰っていきます。一方、カルガモのように一年中見られる留鳥もいます。
カモ類は生態の違いから、大きく淡水ガモ(マガモやカルガモ、コガモなど)と海ガモ(スズガモやホシハジロ、ウミアイサなど)に分けられます。淡水ガモは浅い水辺で逆立ちして水面近くの餌を漁ることが多く、休むときは尾羽を上に向ける傾向があります。海ガモは潜水が得意で、深い水中に潜って餌を採り、休息時には尾羽が水に沈んで水平になります。ただし淡水ガモが海にいたり海ガモが淡水域にいたりすることも珍しくないため、必ずしも見かける場所だけで種類を判断できません。
また、カモ類はオス(雄)とメス(雌)で羽の色や模様が異なるのも特徴です。冬の時期、オスは繁殖期に備えて非常に鮮やかな羽色になりますが、メスは地味な茶色系で模様も控えめです。例えばマガモのオスは頭部が光沢のある緑色で目立ちますが、メスは全身が茶色のまだら模様で、一見するとカルガモとよく似ています。初心者の方は「オスとメスで別の鳥?」と戸惑うかもしれませんが、くちばしの色や顔の模様などに注目すると識別できます(カルガモは顔が明るいクリーム色で嘴先端が黄色、マガモのメスは全体に褐色の斑模様で嘴がオレンジがかっています)。こうしたポイントを押さえておくと、カモ観察がより楽しくなるでしょう。
神奈川県内のカモ類観察に適した探鳥地
ここからは、神奈川県内で冬にカモ類の観察ができる主な探鳥地をいくつか紹介します。都市公園の池から河川敷まで、多彩なスポットがあります。それぞれの探鳥地について環境や特徴、アクセス、見られるカモの種類などを解説します。初心者でも観察しやすい場所ばかりですので、自宅から行きやすいスポットにぜひ足を運んでみてください。
多摩川河口付近〖川崎市〗

多摩川河口付近は、東京都と神奈川県の境を流れる多摩川が東京湾に注ぐ河口部で、川崎市側の堤防沿いから広大な水辺を観察できる探鳥地です。堤防上にはサイクリングロードと歩道が整備されており、視界が開けているため野鳥を探しやすい場所です。冬になると多摩川河口には非常に多くの水鳥が越冬に飛来します。
川の中流から河口にかけて、水面にはスズガモやキンクロハジロなどの潜水ガモ類の大群が点々と浮かんでいます。黒と白のカモがびっしり集まる様子は壮観で、所々にカンムリカイツブリ(潜水ガモではありませんがよく混じっています)の姿も見られます。満潮時にはカモの群れが岸近くまで寄ってくることがあるため、堤防の土手に腰を下ろしてゆっくり観察すると、思いがけず近距離で見られることもあります。また、カモの大群の中にウミアイサ(海ガモのアイサ類)が1羽混じっていることもあるので、双眼鏡で一羽一羽チェックしてみると良いでしょう。
多摩川河口周辺では水鳥だけでなくミサゴ(魚を捕る大型の猛禽類)も冬によく飛来します。運が良ければ、川面にダイブして魚を捕えるダイナミックなミサゴの狩りの瞬間に出会えるかもしれません。捕えた魚を持って堤防近くの杭に留まって食べることもあるので、ミサゴが現れたら動きを追ってみましょう。
環境としては見通しが良い反面、冬は川風が非常に冷たい場所です。長時間いる場合は防寒対策を万全にしてください。また、自転車やジョギングで通行する人も多いので、観察時は通行の邪魔にならないよう配慮しましょう。アクセスは京急大師線「小島新田駅」などから徒歩圏ですが、広範囲を巡るには自転車があると便利です。無料駐車場はありませんが、周辺に有料駐車場があります。都会に近い場所ながら多彩な水鳥が楽しめるスポットとして人気です。
三ッ池公園〖横浜市〗

三ッ池公園(みついけこうえん)は横浜市鶴見区にある県立公園で、その名の通り大小3つの池がある水鳥観察に適した探鳥地です。園内は桜の名所として有名ですが、同時に「かながわの探鳥地50選」に選定されるほど野鳥観察にも優れた場所です。特に冬は水鳥(カモ類)の飛来地として知られ、池には多くのカモが集まります。
上の池・中の池・下の池とありますが、もっともカモ類の数が多いのは広い下の池です。冬になるとマガモやカルガモはもちろん、ヒドリガモやコガモ、ハシビロガモなどさまざまな種類が飛来し、池の水面を賑わせます。運が良ければミコアイサ(パンダガモ)も飛来することがあり、白い姿が確認された年はバードウォッチャーで話題になることもあります。池の周囲には遊歩道が整備されており、約1.4kmのコースを歩きながらカモたちをぐるっと観察できます。
園内ではカモ類以外にもカワセミが池に現れたり、林ではアオゲラ(緑のキツツキ)やシジュウカラなど年間通して様々な野鳥が観察できます。探鳥に疲れたらベンチで休憩しつつ、双眼鏡で水面をスキャンしてみましょう。周囲に人が多くても、カモたちは比較的人慣れしており、池岸近くで採食する姿を見せてくれることもあります。
アクセスはJR鶴見駅やJR新横浜駅からバス利用が便利です(「三ツ池公園北門」「三ツ池公園南門」バス停下車すぐ)。公園内に有料駐車場もあるので車でも訪れやすいです。起伏のある地形ですので歩きやすい靴で訪れてください。街中にありながら多様なカモ類をゆっくり観察できる貴重なスポットとして初心者にもおすすめです。
新横浜公園〖横浜市〗

新横浜公園(しんよこはまこうえん)は横浜市港北区に位置する広大な総合公園で、横浜F・マリノスの本拠地である日産スタジアムに隣接しています。園内北側には「大池」と呼ばれる長い池があり、ここが主なバードウォッチングポイントです。冬鳥の観察に適した探鳥地として知られ、特に冬はこの大池にカモ類を中心とした水鳥が多数越冬にやって来ます。
大池のほとりには柵沿いの歩道が整備されており、池に沿って移動しながら観察が可能です。西側の池畔にはヨシ原やガマ(蒲)の群落があるため、人の姿を隠しながら水鳥に近づくことができます。このヨシやガマをブラインド代わりにしてそっと覗くと、意外な近距離でカモを観察できることがあります。
冬の大池で人気が高いのがミコアイサです。例年数羽~十数羽程度が飛来し、白と黒のコントラストが美しいオスや、茶色い頭のメスたちが池で泳ぐ姿が観察されます。大池は幅がそれほど広くないため、対岸にいるミコアイサも双眼鏡で十分観察できますし、運が良ければヨシ陰からかなり近くに姿を見せることもあります。ミコアイサ以外にもオカヨシガモやハシビロガモなど様々なカモ類が見られ、池に浮かぶ小さな中州(鳥たちの休憩島)ではカルガモやオナガガモ、オオバン(黒い水鳥)が群れて休む姿もよく見られます。
大池には亀甲橋(きっこうばし)という橋がかかっており、橋の上が池全体を広く見渡せるビューポイントです。水面に鳥の姿が少ないときは、中州や水門付近で休んでいないか探してみましょう。また、晴れた冬の日には池や隣の鶴見川上空にノスリ(中型の猛禽類)が舞うこともあります。視線は時折空にも向け、猛禽がいないかチェックするのも一興です。カモたちを驚かせないよう静かに観察していれば、野鳥たちの自然な行動をじっくり楽しめるでしょう。
アクセスはJR横浜線「小机駅」から徒歩5分程度と非常に良好です。園内には駐車場やトイレも完備され、ファミリーでも訪れやすい環境です。ただしスタジアムでイベント開催日には駐車場や周辺道路が混雑するため注意しましょう。都市公園でありながら本格的なカモ観察ができるスポットとして、初心者にも行きやすいおすすめの探鳥地です。
境川遊水地公園〖横浜市・藤沢市〗

境川遊水地公園(さかいがわゆうすいちこうえん)は、横浜市と藤沢市にまたがる境川沿いの広い公園で、今田遊水地・下飯田遊水地・俣野遊水地という3つの遊水池から構成されています。各遊水地にはビオトープ(人工的に造成した生態池)が整備されており、水辺の環境が豊かです。そのため四季を通じて様々な野鳥が観察できますが、特に冬はカモ類を中心とした水鳥の飛来で賑わいます。
3つの遊水地の中でも、とりわけ今田遊水地は水鳥観察がしやすいポイントです。ビオトープ池の水際に沿って遊歩道があり、間近に水面を観察できます。冬になるとヨシガモ、オカヨシガモ、コガモ、ハシビロガモといった多くのカモ類が飛来し、池は一気にカモだらけになります。これらのカモたちは背の高いヨシ(葦)やガマの生えている場所を好んで集まるため、観察するときはヨシ原やガマの多い池の北側・南側を重点的に探すのがおすすめです。ヨシやガマが人の姿を隠すブラインドの役割を果たしてくれるので、茂み越しにそっと双眼鏡を向ければ、リラックスして採食するカモたちの様子を至近で観察できるでしょう。
ビオトープ周辺ではカモ類と一緒にバン(水鷭)やオオバン(大鷭)といったクイナ科の水鳥が見られることもあります。黒っぽい身体に赤い額板(おでこ)が特徴のバンは警戒心が強い野鳥ですが、ヨシやガマの陰からそっと姿を現すことがあります。カモを探しつつ、茂みの近くに黒い鳥影が動いていないかもチェックしてみましょう。
今田遊水地の南側対岸には中洲や浅瀬もあり、冬場にはイカルチドリ(小型のチドリ類)が群れで休んでいることもあります。双眼鏡で砂地をスキャンして、小さな鳥がチョコチョコ走っていないか探してみてください。また、各遊水地とも広い空間が広がるため、運が良ければ上空にノスリなどの猛禽類が飛来する姿も見られます。
境川遊水地公園は各遊水地ごとに駐車場が整備されており、車でのアクセスが容易です。また、横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田駅」から徒歩で下飯田遊水地に出られるほか、小田急江ノ島線「湘南台駅」や「長後駅」からバス便もあります。公園全体が広いので、歩きやすい靴と防寒対策をして訪れましょう。冬には10種類以上のカモが観察できることもあるほど充実したスポットで、初心者からベテランまで楽しめる探鳥地です。
座間谷戸山公園〖座間市〗

座間谷戸山公園(ざまやとやまこうえん)は座間市にある自然度の高い公園で、谷戸(やと)と呼ばれる里山の谷間の地形を活かしたフィールドです。園内には雑木林、草原、小川や湧水池など多様な環境が凝縮されており、冬には多くの野鳥を観察できる探鳥地として知られています。カモ類の生息地としては小規模ですが、水辺環境があるため冬季にはカモも飛来します。
園内の低地にある「水鳥の池」がカモ類観察のポイントです。この池はカワセミ観察スポットとして有名で、木道の観察デッキが池に面して設けられています。秋まではカワセミやトンボを見る人で賑わいますが、冬になると池にマガモやコガモなどのカモ類が姿を見せるようになります。小さな池なのでカモの数は多くありませんが、デッキから近い場所で泳ぐこともあり、双眼鏡がなくても肉眼で観察しやすいです。特にオスのマガモ(頭が緑のカモ)が晴れた日に池面で輝く姿は美しく、初心者でも楽しめるでしょう。
水鳥の池の一角には野鳥観察小屋(ブラインド)が設置されています。池の浅瀬側にあり、ここから静かに覗けば人の気配を抑えて野鳥を観察できます。デッキの上より距離はありますが、その分野鳥も安心しているため、運が良ければ猛禽類のハイタカが水浴びに降りてくる場面などに出会えることもあります。このように、座間谷戸山公園では水辺のカモ類だけでなく、林や草原でジョウビタキやシロハラといった冬の小鳥、さらにはそれらを狙うハイタカなどの猛禽類にも出会える可能性があるのです。
園内は起伏があり、遊歩道には幅が狭く立ち止まり禁止の区間もあります。繁殖期(春〜夏)には一部エリアで立ち止まっての観察が制限されていますので、冬場でも案内板の注意事項は確認しましょう。アクセスは小田急線「座間駅」から徒歩約10分と便利です。駐車場(無料)やトイレも完備されています。里山の雰囲気を残す静かな環境で、少数ながらカモ類の観察も楽しめる穴場スポットです。
相模大堰〖厚木市・海老名市〗

相模大堰(さがみおおぜき)は、相模川中流域に設けられた大きな堰(ダム状の構造物)です。厚木市と海老名市の境界付近に位置し、周辺は川沿いの堤防や原っぱになっていて開放感のある探鳥地となっています。ここは年間を通して野鳥が多い場所ですが、特に冬はカモ類を始め水鳥が数多く越冬に訪れるポイントとして有名です。
相模大堰には管理用の人道橋が架かっており、歩行者や自転車が通行可能です。この橋の上から川の上流・下流の両方向を眺め渡すことができ、探鳥には絶好の展望台となっています(工事等で通行止めの場合もあるので注意)。広い川面では冬になるとヨシガモやヒドリガモといったカモ類の群れがあちこちで見られ、カンムリカイツブリやオオバンも混じって泳いでいます。これらは順光(太陽を背にした方向)で観察できる位置に移動して双眼鏡を当てると、比較的容易に種類を見分けられるでしょう。
中でも注目したいのは、この場所で見られるカワアイサです。相模大堰周辺は神奈川県内でも有数のカワアイサ飛来地で、冬には10羽以上の群れが川に現れることもあります。カワアイサは白と緑のコントラストが美しい大型のカモで、川面を潜水しながら盛んに魚を捕る姿が観察できます。白いオスは遠目にも目立つため、橋の上から肉眼でも「あそこにカワアイサがいるな」と分かるほどです。発見したら双眼鏡や望遠カメラでじっくり観察しましょう。彼らは群れで潜ったり浮かんだりを繰り返すので、そのタイミングを計って見ると面白いです。
相模大堰自体も水鳥の休憩スポットになっています。堰の上に設置されたコンクリートブロックの上で、マガモやカルガモが羽を休めていることがあります。あまり近づきすぎると一斉に飛び立ってしまうため、少し距離を保って静かに観察するのがコツです。橋の上や土手から双眼鏡でそっと眺め、リラックスして眠るカモたちの様子を観察してみましょう。
留意点として、猛禽類のミサゴも冬には堰周辺に高頻度で飛来します。上空を旋回して急降下し、川魚を狙う姿が見られるかもしれません。ミサゴやオオタカなど猛禽が上空に現れると、水面のカモたちは一斉に飛び立ったり草陰に隠れてしまうことがあります。その際は一旦待って、しばらくして落ち着いてからまた戻ってくるのを待つか、別の場所に視点を変えてみると良いでしょう。
アクセスはJR相模線「社家駅」から徒歩5分ほどと便利です。堰の南西側に広場があり、そこに駐車スペースもあります。川風が冷たいため防寒具はしっかり用意し、双眼鏡や望遠カメラを持って行くと楽しさが倍増するでしょう。多種類のカモと迫力あるカワアイサの群れが見られる貴重なスポットとして、一見の価値があります。
寒川取水堰〖寒川町〗

寒川取水堰(さむかわしゅすいせき)は、相模川下流部(高座郡寒川町)にある取水堰です。相模川の水を分岐させる施設ですが、周辺一帯が広い川原と河川敷になっており、主に冬に多くの野鳥が見られる探鳥地として知られています。越冬にやって来る様々な水鳥はもちろん、河川敷に生息する小鳥類やそれらを狙う猛禽類も豊富で、生態系の縮図のような場所です。
寒川取水堰へはJR相模線「宮山駅」から徒歩15分ほどで行くことができます。駅からすぐ川沿いの道に出られ、河川敷を歩きながら向かうことになるのですが、その道中でもたくさんの野鳥が観察できます。冬の朝なら、道脇の藪からシジュウカラやメジロの鳴き声が聞こえ、川沿いの木にノスリ(猛禽類)が留まっていたりすることもあります。移動中も気を抜かず、双眼鏡を首にかけてチラチラ周囲を見渡してみましょう。
取水堰本体は相模川に横たわるコンクリートブロック状の構造で、その少し下流側に神川橋(かみがわばし)という橋がかかっています。この橋を渡れば川の両岸を行き来でき、観察は太陽の位置に合わせて順光側に移動しながら行うと良いでしょう。東岸と西岸それぞれから、堰とその前後の川面を広く見渡せます。
冬の寒川取水堰周辺では、非常に多くの水鳥が川に浮かんだり堰に群がったりしています。数が特に多いのはマガモやコガモといったおなじみのカモたちですが、それに加えてヨシガモ(頭の長い飾り羽が美しいカモ)やカンムリカイツブリも見られます。カモ類の大群に出会ったら、ぜひ双眼鏡で一羽一羽をじっくりチェックしてみましょう。中には珍しい種類が紛れている可能性もあります。このエリアは先述の相模大堰と並んでカワアイサの飛来ポイントとして有名で、大きめの水鳥の群れを見つけたら必ずその中にカワアイサのオス・メスがいないか確認してみてください。
取水堰そのものも水鳥たちの休憩所です。西岸側から近づいてフェンス越しに堰を観察すると、コンクリートブロックの上にカルガモやコサギ(白鷺)がずらりと並んで休んでいる光景が見られます。堰までの距離は東側より西側の方が近く、おすすめです(逆に東側は距離がある分、広範囲を見渡しやすいメリットがあります)。セグロセキレイやハクセキレイが堰の上を歩き回っていたり、春〜夏にはコチドリが走り回っていたりするので、小鳥にも目を向けてみましょう。また堰のそばの水際にカワセミが留まっていることもあるので、青い小さな鳥影を見逃さないようにしてください。
寒川取水堰周辺の河川敷では、冬にベニマシコやホオジロなどの小鳥類が草むらから姿を見せることがあります。さらに、それら小鳥や水鳥を狙ってハイタカやノスリ、チョウゲンボウ(小型のハヤブサ)など猛禽類もしばしば出現します。土手の上から広い範囲を眺めていれば、高確率で猛禽類が飛んでいるのを発見できるでしょう。そして猛禽が現れると往々にして周囲の水鳥が一斉に飛び立つものです。堰周辺のカモたちが急にバサバサ飛び立ったら、「どこかに猛禽がいるな?」と周囲の高い木や鉄塔に目を向けてみましょう。実際、取水堰東側の高速道路沿いに立つ鉄塔は猛禽たちのお気に入りの止まり木で、双眼鏡で覗くと猛禽が留まっていることがあります。
アクセスは前述の通りJR宮山駅から徒歩圏です。またトイレは駅付近か、公園のものを利用すると良いでしょう。広い河原で遮るものがない分、冬は風が冷たいので厚手の上着や手袋をお忘れなく。寒川取水堰は川の自然環境を舞台にダイナミックな野鳥観察が楽しめるスポットです。初心者でも多くのカモ類や猛禽類の動きを一度に観察でき、きっと良い経験になります。
相模川河口〖平塚市・茅ヶ崎市〗

相模川河口(さがみがわかこう)は、相模川が相模湾に注ぐ河口周辺のエリアで、平塚市と茅ヶ崎市にまたがります。川の左岸(東側)が平塚市柳島エリア、右岸(西側)が茅ヶ崎市汐見台エリアに当たり、両岸の堤防や海岸から野鳥を観察できます。多くの水鳥を観察できる探鳥地として、一年を通してバードウォッチングが楽しめますが、冬はやはりカモ類が目立ちます。
河口の堤防上から川面を広く眺めてみると、冬にはヒドリガモ、コガモ、オカヨシガモといった淡水ガモ類が群れているのが見つかるでしょう。川幅が大きいので散在して見えるかもしれませんが、双眼鏡で探せば点在するカモの群れに行き当たります。ある程度近づくこともできますが、堤防からでも十分観察可能です。加えてカンムリカイツブリもよく見られ、カモの群れに混じってスッと潜水したり浮かんだりしています。左岸・右岸どちら側にも視界が開けた地点がありますので、太陽の向きを考えて順光側から探鳥しましょう(午前中なら茅ヶ崎側、午後は平塚側が背中に日を受けて見やすいです)。
この付近では干潮時に小さな干潟や中洲が現れ、時折シギやチドリ類の渡り鳥が立ち寄ります。春や秋の渡りの時期にはキアシシギやチュウシャクシギが観察されることもあります。冬場でも、河口近くの砂利混じりの浅瀬に数羽のハマシギ(小型のシギ)が餌をついばんでいることがありますので、カモ以外の水辺の鳥もチェックしてみてください。なお、干潟狙いで探す場合は河口左岸(平塚側)の砂浜に直接降りられるので、干潮前後に歩いてみると良いでしょう。
水辺以外では、川沿いの枝や堤防の消波ブロックにカワセミが止まっていることもあります。川の流心ばかりでなく、岸近くの構造物の上も時折双眼鏡でスキャンしてみましょう。瑠璃色の小鳥がじっと魚を狙っている姿が見つかるかもしれません。
相模川河口の東側には海岸砂防林と草地が広がっており、このエリアでは留鳥のイソヒヨドリ(磯ヒヨドリ)や、冬鳥のジョウビタキなどを見ることもできます。杭の上や草原の石の上にイソヒヨドリのオス(コバルトブルーの美しい鳥)が佇んでいないか探してみてください。ジョウビタキは林縁に「ヒッヒッ」と鳴きながら現れることが多いので、鳴き声を手がかりに茂みや柵の上をチェックすると発見しやすいです。
さらに海上に目を向けると、たまにオオミズナギドリ(夏鳥ですが冬にも群れで見られることがあります)が飛んでいるのが見えることもあります。高倍率の双眼鏡やフィールドスコープがあれば、沖合を飛ぶ海鳥にも挑戦してみましょう。
アクセス面では、茅ヶ崎市側は柳島しおさい公園付近に駐車場とトイレが整備されており、そこから堤防に出ることができます。平塚市側も漁港の駐車場があります。広いエリアなので、歩きやすい靴と寒風を防ぐ服装で出向きましょう。相模川河口は、海と川が交わる環境ならではの多様な野鳥が観察できるスポットです。身近なカモ類から海鳥まで、初心者がフィールドを広げるのにもってこいの探鳥地と言えるでしょう。
酒匂川河口〖小田原市〗

酒匂川河口(さかわがわかこう)周辺は、小田原市を流れる酒匂川の河口一帯のエリアです。西湘地域に位置し、富士山や箱根連山を遠望できる開放的な河川敷・海岸が広がっています。ここも一年中多くの野鳥が観察できますが、中でも冬はカモ類や水鳥の宝庫となります。県央・県東の探鳥地に比べ人出が少なく、落ち着いて観察できる穴場スポットです。
主に酒匂川の西岸(小田原市側)が観察しやすく、午後には順光の良い条件で河口全体を見渡せます。川沿いには砂利混じりの道がありますが比較的歩きやすく、視界を遮るものも少ないため、野鳥を探しやすいでしょう。注意点として、大雨の後などは川の水量が増して流れが急になり、野鳥がとどまりにくくなるため、雨上がり直後は避けるのが無難です。
冬の酒匂川河口では、ウミアイサやカワアイサといったアイサ類(魚食のカモ類)が見られる点が大きな魅力です。河口周辺の海上にはカンムリカイツブリやウミアイサが浮かんでいることがあり、川から海沿いにかけて双眼鏡で探してみてください。また、この周辺はカワアイサの飛来ポイントとしても有名です。特に酒匂川では河口からやや上流に位置する飯泉取水堰(いいずみしゅすいせき)や、JR東海道線・新幹線の鉄橋付近でカワアイサの群れがよく観察されています。そのため、河川敷を歩く際には川面に目を凝らし、白い大きなカモが潜水を繰り返していないかチェックしましょう。カワアイサは流れの緩やかな場所で潜水しながら餌を取っていますが、時折コンクリートブロック状の構造物に上がって休むこともあります。河川敷に点在するブロックの上や浅瀬で、水鳥が羽を休めているのを見つけたら、その中にカワアイサが混じっていないかしっかり確認してみると良いでしょう。
酒匂川河口には小さな中洲や干潟も形成されます。渡りの時期にはキアシシギなどが立ち寄りますが、冬にもハマシギの群れが見られることがあります。イソシギは留鳥として川岸のあちこちで一年中見られますので、こちらも探してみてください。
河口周辺のコンクリートブロックや杭の上はカワセミのお気に入りポイントでもあります。鮮やかなブルーの鳥影がちょこんと留まっていないか、双眼鏡でじっくり探しましょう。夏には多数飛来するコアジサシ(小型のカモメの仲間)も、この場所では夏鳥として有名です。冬場は見られませんが、「ここに夏にはコアジサシが来るのか」と思いを馳せながら歩くのも楽しいでしょう。冬の河川敷ではタヒバリ(セキレイの仲間)が地面をチョコマカ歩き回っていることも多いです。利用者の少ないサッカーグラウンドや野球場の地面で、小さな鳥が群れているのを見つけたらタヒバリかもしれません。
アクセスはJR東海道線「鴨宮駅」から徒歩約15分で河川敷に出られます。車の場合、河川敷西側にグラウンド利用者向けの駐車場があり、空いていれば駐車可能です。トイレは周辺の公園施設を利用できます。酒匂川河口は富士山を背に野鳥観察ができる風光明媚なスポットで、特にカワアイサとウミアイサの両方が狙える点で貴重です。人混みを避けてゆっくり水辺の鳥たちと向き合いたい方にとって、神奈川西部を代表する冬の探鳥地と言えるでしょう。
冬のカモ観察を楽しむコツと注意点
冬季にカモ類を観察する際には、野鳥にストレスを与えず快適に楽しむためのコツや注意点があります。ここでは初心者の方に知っておいていただきたいポイントをまとめます。自然の中でのマナーも守りつつ、冬のカモ観察を充実させましょう。
太陽の位置に注意して観察
広い湖沼や河口・海岸でカモを見る場合、太陽の位置(光線の向き)がとても重要です。逆光では鳥の姿が真っ黒に見えてしまい、種類の判別もしにくくなります。できるだけ順光(太陽を背にした方向)になる岸辺や堤防から観察するようにしましょう。例えば午前中なら東側・北側から、午後は西側・南側から水面を見ると良い条件になります。紹介した探鳥地でも、橋を渡って反対岸に行ける場所や、広範囲に歩ける場所では、その時々で最適なポジションに移動することが大切です。また日没が早い冬は観察できる時間帯も短いので、午前中から余裕を持って出かけることをおすすめします。
観察ポイントによっては、野鳥観察窓や観察小屋が設置されていることがあります。そうした施設はあらかじめ日差しの角度や野鳥からの見えにくさを考慮して作られているため、大いに活用しましょう。観察窓越しに静かに待っていると、人に警戒しているカモでも意外な近さで観察できることがあります。野鳥側からも人影が見えにくくなっているので、カモたちものんびりリラックスしている様子が見られるでしょう。
混群(こんぐん)に注目し、一羽ずつ確認
冬に飛来するカモ類の多くは群れ(群翔)で行動しますが、ほとんどの場合複数種混ざり合った「混群」を形成しています。1種類だけの群れはむしろ少なく、マガモの群れにカルガモが混じっていたり、コガモとヒドリガモが一緒にいたりと、色々な組み合わせが見られます。したがって、大きなカモの群れに出会ったら、ぜひ「全部同じ種類かな?」と決めつけずに一羽一羽の特徴を確認してみてください。最初は難しく感じるかもしれませんが、例えば「潜らないで尻尾を上に上げているカモ(淡水ガモ)と、潜水を繰り返すカモ(潜水ガモ)が混じっているな」など、大まかな違いから気付くこともあります。
混群を観察するコツとして、図鑑や野鳥識別アプリなどで事前に識別ポイントを頭に入れておくと良いでしょう。しかし種類が多くて一度には覚えきれないものです。そんなときはまず*よく潜るカモ」と「潜らないカモ」といった大きな分類から意識してみましょう。泳ぎ方や行動パターンを観察するだけでも、「あのグループは潜水ガモの仲間だな」「こちらは淡水ガモだな」と見当が付きます。そして徐々に「頭が緑だからマガモかな?」「白い体が目立つのはミコアイサだ!」というように細部まで分かるようになっていきます。
なお、大群の中で特定の個体をじっくり見ていて目を離してしまうと、再び同じ個体を見つけるのが大変です。特にスズガモの群れにコスズガモ(似た種類)が混じっている場合など、識別に時間がかかると見失ってしまうこともあります。そのため、本格的に観察する際は三脚に据えたフィールドスコープ(高倍率の望遠鏡)を使うのがおすすめです。スコープで群れを固定しておけば、じっくり一羽ずつ確認できます。初心者のうちは双眼鏡で十分ですが、ゆくゆく興味が深まったら検討してみても良いでしょう。
海ガモは荒天と満潮がチャンス
海岸や湾内で観察する海ガモ類(主に潜水ガモ)は、普段は沖合に散らばっているため遠すぎて見づらいことが多いです。しかし、風の強い日や満潮時は彼らが岸近くに寄ってくる絶好のチャンスになります。一般にバードウォッチングは風が穏やかな日の方が良いとされますが、海ガモ類に限っては荒天が狙い目なのです。
風が強く海が荒れる日は、スズガモやビロードキンクロ(海ガモの一種)などは波を避けて堤防の内側や港の中など比較的穏やかな水面に集まる傾向があります。いつもは遥か彼方に見えていたカモたちが、驚くほど近くでプカプカ浮かんでいることもあります。ただし風の強い冬日は人間にとってもかなり過酷ですので、防寒装備を十分に整えてから臨みましょう。堤防上は特に風がまともに当たり、三脚が倒れるほどの突風もあります。機材はしっかり押さえ、安全第一で観察してください。
加えて満潮時もポイントです。干潟が現れるような河口や浅場では、引潮のときカモたちは沖に離れてしまいます。しかし満潮に近づくと、餌を求めて岸辺近くに集まることが多いです。特に干潟の広い場所では、満潮時でないとカモとの距離が遠くなりすぎます。事前に潮位表を調べ、満潮の時間帯を狙って現地に行くと効率的です。「風が強い日」と「満潮時」が重なればベストですが、どちらか一方でも活用してみましょう。
なお、海ガモ類を観察する際には、彼らが顔を背中の羽に突っ込んで眠っていることが多い点に留意してください。波間に浮かぶ黒っぽいカモが、頭を丸めてなかなか顔を見せてくれない…そんな状況はよくあります。種類の判別に時間がかかるかもしれませんが、焦らず根気よく待ちましょう。双眼鏡やスコープを構えていると、ふと顔を上げた瞬間に識別ポイントが見えることがあります。
猛禽類の出現に注意
冬のカモ類がたくさん集まる場所には、そのカモたちを狙う猛禽類も出現しやすくなります。カモの群れにとって、オオタカやハヤブサなど猛禽類は天敵です。そのため、上空に猛禽が飛来するとカモたちは一斉に飛び立ったり、葦原などに隠れてしまうことがあります。観察中、突然カモが一斉に騒ぎ立てて飛び去った場合、猛禽類が近くに姿を見せたサインかもしれません。
そのような時は、視野を広げて周囲の高い木のてっぺんや電柱・鉄塔の上などを探してみましょう。不自然にカモの数が減って静かになった場所では、近くの木にオオタカが留まっていた…ということもあります。猛禽類も非常に魅力的な観察対象ですので、カモを待つ合間に双眼鏡で木立の上や空をチェックしてみるのはおすすめです。「カモ観察は猛禽観察とセット」と心得ておくと、思わぬ収穫があるでしょう。
もし猛禽類が出現してカモたちが長時間戻ってこない場合は、思い切って観察場所を変えてみるのも手です。例えば川の下流側に飛んで行ったなら、少し下流へ移動すればまた落ち着いているカモが見られるかもしれません。あるいは別の池にハシゴしてみるなど、フットワーク軽く対応すると、時間を有効に使えます。
他の野鳥や周囲の人への配慮
カモ類を観察していると、同じ水辺でカモ以外の野鳥にも出会えることが多いです。例えばカモと一緒に泳ぐオオバンやバン、周囲に飛来するユリカモメ(カモメ類)、岸辺の草むらから顔を出すクイナ、近くの茂みに現れる小鳥(ホオジロ類やベニマシコなど)も観察できるかもしれません。カモを待っている間も、ぜひ周囲に目を配り、他の野鳥の存在にも気付いてみてください。冬の水辺はカモ類が主役ではありますが、それと同時に野鳥観察の総合舞台でもあります。視野を広げれば観察の充実度が増すでしょう。
また、観察マナーとしては野鳥と周囲の人々への配慮が大切です。野鳥に対しては、なるべく驚かせないようゆっくり静かな動きを心がけます。近づきすぎず、大声を出さず、双眼鏡やカメラでそっと観察しましょう。特に休息中のカモを無理に近距離で撮影しようとすると、一斉に飛ばしてストレスを与えてしまいます。紹介した探鳥地には観察デッキや指定の観察場所がある場合も多いので、可能な限り定められた場所から観察するようにしてください。
人に対しては、フィールドではハイカーや釣り人、地元の方々など鳥以外の目的で訪れている人もいます。通行の邪魔にならないよう三脚の設置場所に注意したり、狭い道では譲り合って歩きましょう。座間谷戸山公園のように「繁殖期に立ち止まり禁止」のルールがある所では、それに従うことも重要です。他のバードウォッチャーがいる場合は、情報交換をしてみるのも楽しいですが、大勢で占拠して談笑するなどは避け、譲り合いの気持ちを持つと良いでしょう。
冬のバードウォッチング初心者向け持ち物・服装アドバイス
最後に、冬にカモ類観察をする際の持ち物や服装について、初心者向けのポイントをお伝えします。冬場の野鳥観察は寒さとの戦いでもありますが、装備をきちんと整えれば快適さが格段に違います。また、野鳥に接近するための工夫や、安全に楽しむための道具も押さえておきましょう。
- 防寒着・防寒小物:冬の水辺は想像以上に冷えます。防寒対策は最重要です。ダウンジャケットや厚手のコートなど暖かい上着を着込み、インナーもヒートテックなど保温性の高いものを重ねましょう。ただし、長時間じっとしていると体は冷えてくるため、貼るカイロやポケットカイロを準備しておくと安心です。手先が冷えると双眼鏡の操作もしにくくなるので、防寒手袋も必須です。最近は指先に特殊な素材がついて双眼鏡やスマホの操作ができるトレッキング用グローブなどもありますので、そういったものを活用すると便利です。帽子や耳あて、ネックウォーマーなどで頭や首筋の保温もお忘れなく。場合によっては顔全体を覆うフェイスマスクも有効ですが、人の多い公園では怪しまれるかもしれないので、人の少ないフィールドで使うようにしましょう。
- 滑りにくい靴:野鳥観察では歩く距離が長くなったり、不整地を歩くこともあります。冬は足元が濡れていたり凍っていたりする場面もあるので、滑りにくく足首までホールドできる靴が望ましいです。履き慣れたスニーカーでも構いませんが、できればトレッキングシューズや防水ブーツだと安心感が違います。雪が積もるような場所に行く場合は、靴に装着できる滑り止めスパイクを携行すると万一の凍結路でも対応できます。一般的な探鳥地であれば、厚手の靴下と歩きやすい靴で十分ですが、「寒さで足先が痛い」ということがないよう防寒も意識しましょう。
- 双眼鏡(必須)とカメラ:野鳥観察において双眼鏡は必須の持ち物です。肉眼だけでは遠くのカモの細かな特徴は分かりません。初心者用でも構いませんので、できれば倍率8~10倍程度の双眼鏡を用意してください。首から下げてすぐ使えるようにし、レンズが曇らないよう使用前には防寒マスクやマフラーで息がレンズにかからない工夫を。写真撮影に興味があるなら、望遠コンデジや一眼レフ+望遠レンズを持参しても良いですが、まずは双眼鏡でしっかり観察することをおすすめします。カメラを使う場合はレインカバーも用意しましょう。雪や水しぶきで機材が濡れると故障の原因になるため、急な天候変化にも対応できるカバーがあると安心です。
- 観察補助用品:その他あると良いものとして、野鳥図鑑や識別アプリがあります。初めて見るカモの種類に出会ったとき、その場で調べられるとモヤモヤが解消します。紙の図鑑は荷物になりますが一冊カモ類特集の雑誌などを持っていっても良いですし、スマホに野鳥識別アプリを入れておけば簡単に検索できます(電池切れに注意)。また、野鳥の名前や数を記録するメモ帳やペンがあると観察データを残せます。最近はスマホアプリで記録する方も多いですが、手書きでメモしておくと記憶に残りやすくなります。
- 飲み物・軽食:冬場は長時間外にいると体が冷えるので、温かい飲み物を用意しましょう。魔法瓶に入れたホットドリンクは体温維持に効果的です。観察に夢中になっているとつい水分補給を忘れがちですが、適度に喉を潤してリラックスすることも大事です。公園内に売店がない場所も多いので、事前に用意していくと安心です。軽食やおやつもあれば、小腹が空いても元気に動けます。
- エチケット用品:フィールドによってはトイレが近くになかったり、冬の冷えでお腹の調子が悪くなることもあります。事前にお手洗いは済ませておくのが基本ですが、念のためポケットティッシュやウェットティッシュを持参しましょう。場合によっては簡易トイレ等を携帯する方もいますが、普通の探鳥地ではトイレが整備されているケースが多いです。心配な方は常備薬(胃腸薬や鎮痛剤)を持っておくといざという時安心です。特に遠出する際は早起きでお腹の調子が乱れがちなので、市販の下痢止め薬をバッグに忍ばせておくと心強いでしょう。
- 安全対策用品:冬の野外活動では日没後は一気に暗く寒くなります。時間には余裕を持ち、日暮れ前に行動を終えるのが基本ですが、念のため小型の懐中電灯があると便利です。足元を照らしたり、緊急時の合図にもなります。また、スマホのモバイルバッテリーも持っておくと安心です(寒冷地ではバッテリー消耗が早いため)。荷物はリュックなど両手が空く形で持ち運び、動きやすくしましょう。
以上、冬のカモ観察に向けた装備と服装のポイントを挙げましたが、一番大切なのは無理をしないことです。寒さを我慢しすぎたり、体調が悪いのに出かけたりすると、せっかくのバードウォッチングも楽しめません。しっかり準備を整えて、安全と健康を確保しつつ冬ならではの野鳥観察を満喫してください。初心者の方は最初は近場の公園の池などから始め、徐々に遠方のフィールドにも挑戦してみると良いでしょう。
まとめ:冬の神奈川県はカモ類観察の絶好のシーズンです。カモ類の基礎知識を踏まえ、紹介した探鳥スポットでぜひ実際に観察を楽しんでみてください。マガモやコガモといったお馴染みのカモから、運が良ければミコアイサやカワアイサといった少し珍しい種類まで、多彩な出会いが待っています。防寒とマナーに気を付けつつ、双眼鏡片手に冬の探鳥地へ出かけましょう。最初は識別が難しく感じても、何度も観察するうちにカモ類の魅力がきっと分かってくるはずです。冬ならではの爽やかな空気の中、水辺に集うカモたちとの出会いを楽しんでください。あなたのバードウォッチングライフの素敵な第一歩となりますように。
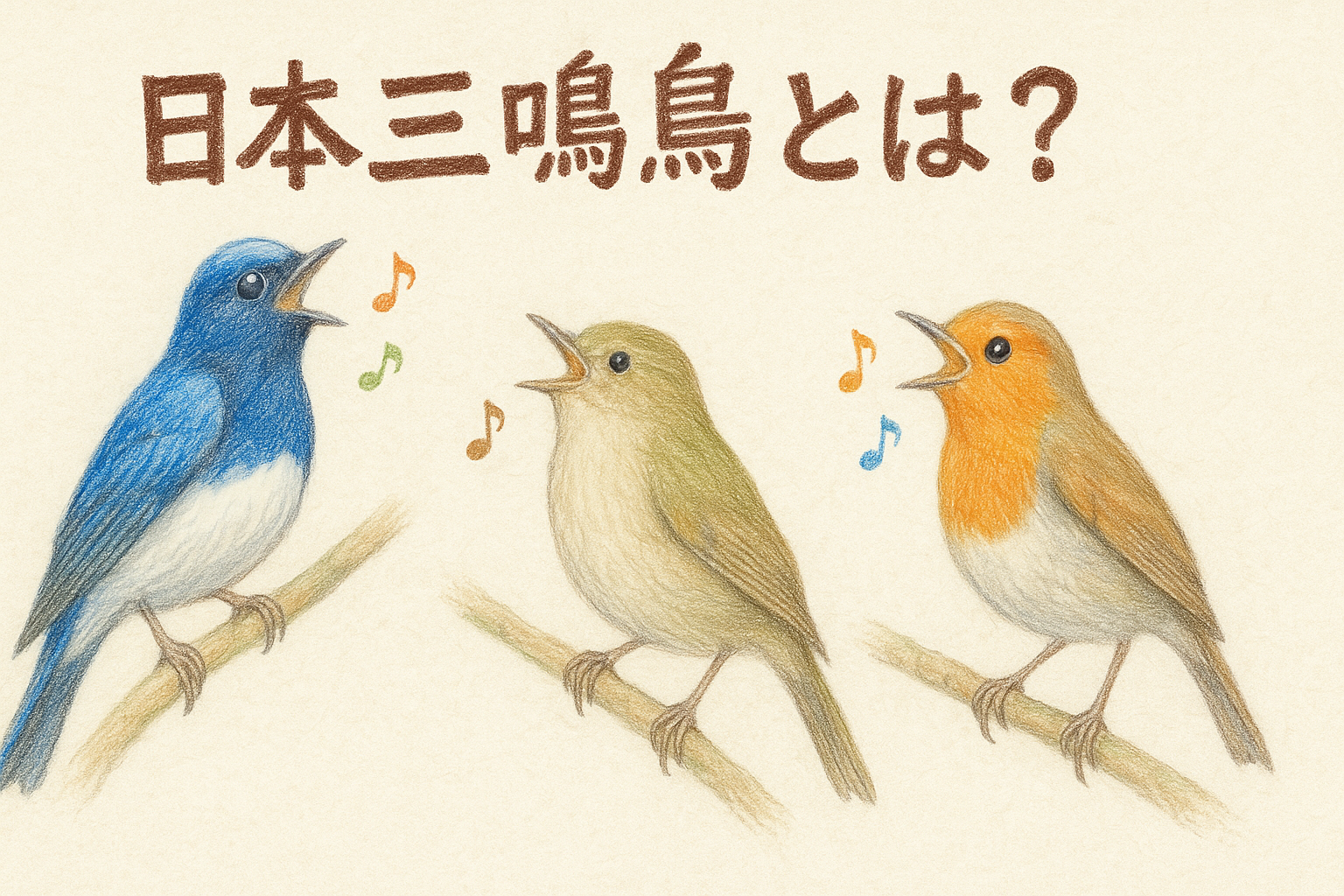

コメント