
日本の田園地帯には、四季折々でさまざまな野鳥が訪れます。広々と開けた田んぼは野鳥観察初心者にも比較的探しやすい環境で、地面を歩き回る鳥の姿をじっくり観察することができます。本記事では、春・夏・秋・冬それぞれの季節に田んぼで観察できる代表的な野鳥と、その特徴や見どころを初心者向けに紹介します。また、通年で見られる野鳥や、初心者のための野鳥観察のコツとマナーについても解説します。季節ごとに変化する田んぼの野鳥たちの魅力を存分に楽しんでみましょう。
春に見られる野鳥
春の田んぼは雪や霜が解け、田植えの準備が始まる季節です。水を張ったばかりの水田や、苗が低いうちは、旅の途中で立ち寄る渡り鳥や繁殖のためにやって来る夏鳥を観察する絶好のチャンスです。ここでは、春に田んぼでよく見られる主な野鳥を紹介します。
ムナグロ

ムナグロは春と秋の渡りの時期に田んぼや干潟に飛来する旅鳥(渡り鳥)です。チドリ科の鳥で、夏羽では名前の通り胸から腹が黒くなるのが特徴です。春の田んぼでは冬羽から夏羽へ換羽中の個体が多く見られ、まだら模様で土に溶け込むような保護色になるため発見が難しいこともあります。ムナグロは数羽から大群で行動することが多いので、上空を群れが飛んでいたら着地場所を確認してみましょう。田植え直後で水の張ってある視界の開けた田んぼでは、ムナグロの群れが降り立つ姿を観察できる可能性が高まります。なお、干潟にも立ち寄りますが、干潟にはよく似たダイゼンがいるため、野外では双眼鏡で羽の模様をよく確認すると良いでしょう。
ツバメ

春を告げる渡り鳥の代表格であるツバメは、毎年春に東南アジア方面から日本に渡ってくる夏鳥です。田園地帯の空を低く滑空しながら昆虫を捕食する姿がよく見られ、軒下に巣を作って子育てする様子も身近に観察できます。繁殖期のオスはさえずりながら飛び回り、夕方には電線にずらりと並ぶこともあります。春の田んぼ周辺で忙しく飛び回るツバメたちは、日暮れ時になると地表近くに降りて休むこともあり、間近で観察できる機会もあります。夏にかけて雛(ひな)を育て、秋になると渡りの群れを作って南方へ帰って行きます。
ヒバリ

ヒバリは一年中見られる留鳥ですが、春先に特に目立つ野鳥です。春の田んぼや畦道(あぜみち)では、オスのヒバリが高く舞い上がって「ピーチクパーチク」とさえずり飛翔(ひしょう)する姿がよく確認できます。さえずりながら天空高く舞い上がり、ゆっくり降下する独特の囀り(さえずり)飛行は、春の風物詩ともいえるでしょう。地上に降りたヒバリは、地味な茶色の羽色をしていますが、胸に淡い斑(ふ)模様があり近づくと確認できます。田んぼの畦に降り立っている姿もよく見かけますが、土と同化し見つけにくいため、動きやさえずりに注目して探してみましょう。春は繁殖期にあたり縄張り意識が強く、同じ草原性の野鳥であるセッカも上空を舞いながらさえずりますが、ヒバリの方が一回り体が大きく声質も全く異なるため、見慣れれば区別は容易です。
コチドリ

コチドリはムナグロと同じチドリ科の野鳥で、春に日本に渡来して繁殖する夏鳥です。小型のチドリで、目の周りの黄色いアイリング(アイシャドウのような輪)が特徴的です。田んぼや河原などの開けた地面を好み、砂利地や水の浅い休耕田でピヨピヨと鳴きながら走り回る姿が観察できます。田んぼでも春に多く飛来し、水田や砂地など各所で見られています。天敵から身を守るため、雛や卵に危険が迫ると親鳥が傷ついたふりをして敵を誘引する擬傷行動を見せることも知られています。コチドリも数羽で行動することが多いので、一羽見つけたら近くに仲間がいないか探してみましょう。
夏に見られる野鳥
夏の田んぼは稲が青々と生い茂り、水辺には生き物が溢れる季節です。繁殖のために飛来した夏鳥や、田んぼで子育てをする留鳥たちで賑わいます。夜明けとともに鳥たちのさえずりが聞こえ、日中は強い日差しの中で水辺の鳥が活発に活動します。ここでは、夏の田んぼで観察できる代表的な野鳥を紹介します。
アマサギ

アマサギは夏鳥として日本にやって来るサギ科の野鳥で、田んぼや湿地帯でよく見られます。普段見慣れた白いサギ(コサギやダイサギなど)より一回り小さいのが特徴です。夏羽になると頭や首、背中が美しい亜麻色(薄いオレンジ色)に染まり大変目立つため、「黄毛鷺(こうもうさぎ)」の異名もあります。一方で冬羽(非繁殖期)では全身が真っ白になり、チュウサギなど他の白いサギ類とよく似てしまうため識別には注意が必要です。夏羽のアマサギを観察したい場合は、多くの個体が夏羽になる6月頃が狙い目です。田んぼでアマサギの群れを探す際は、見渡しの良い土手や堤防に上がって広範囲を双眼鏡でチェックすると良いでしょう。アマサギは小さな群れで行動することが多く、田植え直後で稲が低い5月頃には田んぼでエサをついばむ群れを見つけやすくなりま。夏は他のサギ類と混じってコロニー(集団繁殖地)で子育てを行うため、繁殖地近くではコサギやアオサギに混ざった姿を見ることもできます。
チュウサギ

チュウサギはダイサギ(大鷺)とコサギ(小鷺)の中間程度の大きさ(全長65cm前後)の白鷺で、夏に日本へ飛来する夏鳥です。かつては個体数が減少していましたが、近年は各地の水田で夏にその姿が見られるようになってきました。田んぼでは単独か少数で行動し、小魚やカエル、バッタなどを捕食します。留鳥のダイサギやコサギに比べ夏限定で見られるため、田んぼに白いサギが増えるこの季節は「チュウサギも来ているかな?」と注目してみると良いでしょう。アマサギ同様、稲が伸びきっていない初夏の田んぼでは見つけやすいですが、稲が繁茂すると背の低いチュウサギは隠れてしまうことがあります。
タマシギ

タマシギは日本の水田で繁殖する数少ないシギ(鴫)類の一種です。全長約25cmのずんぐりした体型で、英名をGreater Painted-snipeといい、オスよりメスの方が羽色が美しいことで知られています。草むらの多い湿った田んぼを好み、ペアで縄張りを持って繁殖します。メスがオスに求愛し、卵を産んだあとの抱卵や育雛(いくすう)は主にオスが行うという珍しい習性を持っています。田んぼで観察できることは稀で、その隠れんぼ上手な性質から見つけるのはやや難しい鳥です。稲が伸び切ってしまう真夏には草陰に隠れてしまうため、タマシギを探すなら田植え直後の春先、水田の水位が低く稲が短い時期がおすすめです。早朝や夕方など鳥の活動が活発な時間帯に、水際の泥地を双眼鏡でじっくり探してみましょう。タマシギは警戒心が強いため、人影に気付くと草むらに素早く身を隠します。静かに観察し、もし飛ばれてしまっても付近にまた降りることが多いので、慌てずに周囲を探してみると良いでしょう。
ヒクイナ

ヒクイナはクイナ科の小型の水鳥で、全長20cmほどしかない茶褐色と赤色の体色をした鳥です。田んぼ周辺の草むらに生息し、「キュッ、キュッ」という鋭い鳴き声を発しますが、その姿はなかなか見ることができません。夏の田んぼ脇にある背の高い草むらの中に潜んでいることが多く、姿を隠すのが非常に上手な野鳥です。春から初夏にかけて繁殖期になると繁殖相手を求めて活発になり、ときおり開けた田んぼの方へ歩き出てくる個体が観察できます。ヒクイナを探すコツは、草が生い茂った湿地の縁にある浅い水たまりやぬかるみを注意深く見ることです。運が良ければ、草陰からそっと姿を現しエサをついばむヒクイナに出会えるでしょう。非常に用心深く、人の気配ですぐ草むらに逃げ込んでしまうため、遠くから双眼鏡で静かに観察することが大切です。
オオヨシキリ

夏の田んぼ周辺でひときわ大きな声で鳴き続けるのがオオヨシキリです。スズメ目ヒタキ科の鳥で、ヨシ原(葦が茂る湿地)を主な生息地とします。日本には夏鳥として渡来し、田んぼ脇のヨシ原で繁殖します。茶色い体に白い喉を持ち、くちばしが大きく開けてさえずる姿は夏の風物詩です。「ギョシギョシ…」と濁った大きな声でさえずり(この声から「行々子(ギョギョシ)」という異名があります)、昼夜問わず囀るため、近くに生息していればすぐに存在に気付くでしょう。オオヨシキリは縄張り意識が強く、ヨシ原では隣接する個体同士が負けじと大声合戦を繰り広げます。見つけるコツはまず声を頼りにし、ヨシ原の上部に止まっている個体を双眼鏡で探すことです。運が良ければ、ヨシ原から飛び出して田んぼ上空を横切る姿や、餌の昆虫を捕まえて巣に運ぶ様子が観察できるでしょう。
セッカ

セッカはスズメ目ウグイス科のとても小さな野鳥です。茶色い羽色に白い腹を持ち、地味な姿ですが、その習性は大変ユニークです。主に留鳥または漂鳥として、日本では一年中見られますが、平地の草原や田園地帯では繁殖期の春から夏に特に目立ちます。繁殖期になると、オスは「ヒッヒッヒッ…チッチッチッ…」という軽快なさえずりを繰り返しながら空高く舞い上がり、上空でさえずり飛翔をします。さえずり飛翔を終えると、近くの低木や草の上に一旦止まることも多く、この動きを利用すると比較的見つけやすいでしょう。セッカは同じようにさえずり飛翔を行うヒバリと生息地が重なることが多いですが、ヒバリの方が体が大きく声も複雑であるため、見慣れれば区別は容易です。冬季は背の高い草むらやヨシ原に隠れて静かに過ごすため発見が難しくなりますが、留鳥として生息している地域では年中観察のチャンスがあります。
コシアカツバメとイワツバメ


夏の田んぼの上空を舞うツバメの仲間には、コシアカツバメとイワツバメという種類もいます。コシアカツバメはその名の通り腰(こし)の部分が赤褐色のツバメで、夏鳥として渡来し民家の軒下や橋の下などに巣を作ります。飛翔力が強く、山間部から平地まで幅広く飛び回りますが、個体数はそれほど多くありません。イワツバメは腰が白色で、断崖や人工建造物の壁面などにツバメのような巣を作る夏鳥です。翅(はね)が短めで素早く羽ばたく飛び方をし、都市部でも見られることがあります。どちらも田んぼ上空で昆虫を捕食し、水が入った用水路や水たまりで水飲みや水浴びをすることもあります。見分け方は、飛んでいる時の腰の色(赤いならコシアカ、白いならイワツバメ)や、尾の形状(コシアカツバメは尾がやや長く二又が深い)などがあります。ツバメ類は夕方になると電線に集まる習性があるため、日没前に田んぼ周辺の電線をチェックすると複数種が混ざって止まっている様子が観察できるかもしれません。
秋に見られる野鳥
秋の田んぼは稲刈りのシーズン。収穫後の田んぼには落ち穂が残り、多くの野鳥たちにとって格好の餌場となります。また、夏に繁殖を終えた鳥たちが南へ渡りに旅立つ時期でもあり、春に見られたシギ・チドリ類が再び立ち寄ることもあります。さらに、晩秋になると冬鳥たちが北から飛来し始め、田んぼの景色はまた変化していきます。ここでは、秋の田んぼで注目したい野鳥について紹介します。
タシギ

タシギはチドリ目シギ科の一種で、田んぼに生息する代表的なシギの仲間です。その名の通り田んぼで見られることが多く、春と秋の渡りの時期や冬に観察されます。長い嘴(くちばし)を泥中に突っ込んでミミズや小さな水生生物を探して食べます。体の羽模様は褐色と黒の縞模様があり、枯れ葉や土塊に紛れる見事な保護色となるため、動かないと見つけるのが難しい野鳥です。一見タシギがいないように見える田んぼでも、刈り取った稲株の陰などを双眼鏡でじっくりチェックしてみましょう。春秋の渡りの時期には、タシギに似た別種(ハリオシギやチュウジシギなど)が混じることもありますが、そうした旅鳥のシギ類は冬になるとほとんど見られなくなるため、タシギの観察にはむしろ他のシギが少ない冬が適しています。タシギは単独でいる印象がありますが、実は時に10羽以上の群れを作る場合もあります。そのため、一羽見つけたら周囲に他の個体が伏せていないか必ずチェックしましょう。稲刈り後の湿った田んぼや蓮田(はすだ)などが格好の休息・採餌場となるので、秋から初冬にかけて水気の残った田んぼを探すとタシギに出会える可能性が高まります。
渡りの季節と収穫後の田んぼの野鳥たち
秋は春と同様に多くの鳥たちが移動する季節です。ムナグロなど春に渡来したチドリの仲間が再び立ち寄り、夏鳥だったツバメたちは家族群れで電線に集まった後、南への長旅に出ます。収穫後の田んぼでは、スズメ(雀)やムクドリ(椋鳥)の大群が落ち穂や虫を求めて地面をついばむ姿が見られます。特にスズメは一年中見られる身近な野鳥ですが、秋から冬にかけては群れの規模が大きくなり、数百羽にもなる大集団で行動します。日中、刈り取った稲わらの間で餌を探し、夕方になると安全なねぐら(竹薮や茂み)に集結して一夜を過ごします。ムクドリもまた畑や田んぼで群れを作る代表的な野鳥で、地表を跳ね歩きながら昆虫や落ちた穀物を盛んについばんでいます。彼らが一斉に飛び立ち、電線や林にとまって騒ぐ様子は、秋の夕暮れによく見られる光景です。
また、初秋の田んぼにはセイタカシギやアオアシシギなどの旅鳥の水鳥が立ち寄ることもあります。休耕田に水が残されている場合、そこがシギ・チドリ類の貴重な中継地となります。さらに、晩秋になるとタゲリやツグミなど冬鳥の姿もぼちぼち見られ始め、季節の移り変わりを感じさせてくれます。秋の田んぼは、生き物たちにとって収穫の恵みが溢れるとともに、渡り鳥たちの休息の場ともなっており、春とはまた違った賑わいがあります。
冬に見られる野鳥
冬の田んぼは一見寂しげですが、実は野鳥観察には絶好のシーズンです。稲が刈り取られて視界が開けるため地上の鳥を発見しやすく、餌を求めて集まる冬鳥たちや、越冬のために飛来した鳥たちが数多く見られます。また、小鳥を狙って猛禽類(もうきんるい)も姿を現すなど、生態系のドラマが展開されます。ここでは、冬の田んぼで観察できる代表的な野鳥を紹介します。
ケリ

ケリはハト大ほどのチドリ科の大型の水辺の鳥で、田園地帯を代表する留鳥です。一年中同じ地域に留まって繁殖しますが、個体によっては冬季に移動するものもおり、普段ケリがいない地域の田んぼでも冬に見られることがあります。全身は灰褐色で、腹面が白く、胸に黒い帯があるのが特徴です。足が長く胴体も高いため、稲が伸びきっていない田んぼであれば遠くからでも見つけやすいでしょう。繁殖期の春や初夏にはつがいや単独で行動し、冬は群れを形成して行動します。春先の田んぼでは1羽のケリが1枚の田んぼを縄張りにしている光景も見られます。ケリは非常に警戒心が強い野鳥として有名で、繁殖期には自分の縄張りに入ってくる猛禽類やカラスを激しく追い払います。頭上を「キリリ、キリリ」という甲高い声で鳴きながら飛び回る姿は迫力があり、その後どの田んぼに降り立つかを確認しておけば観察は容易です。冬場は10羽以上の群れでいることもあり、一度にたくさんのケリを観察できます。ただし冬は隠れる草も少ない分、人に気付くとすぐ飛び去ってしまうため、双眼鏡やフィールドスコープで遠くから静かに観察するのがおすすめです。
タゲリ

タゲリはケリと同じチドリ科ですが、冬鳥として日本に飛来する渡り鳥です。頭に長い黒色の冠羽(かんう)を持ち、光沢のある緑色の羽と白いお腹のコントラストが美しい鳥です。田んぼに好んで飛来し、その名の通り田んぼでよく見られる冬鳥となっています。通常は群れで行動することが多く、広い田園地帯を飛び回っている姿が見られます。上空を野鳥の群れが飛んでいたら、降り立った先がないか目で追ってみましょう。冬の田んぼには稲がなく見通しが良いので、タゲリの群れが降りた場所を見つけやすいはずです。タゲリのいる田んぼでは、近くにノスリやチュウヒなどの猛禽類が現れることもあります。猛禽類が接近するとタゲリは「ミュー、ミュー」という猫のような声で鳴きながら一斉に飛び立つので、猛禽が上空を飛んでいないかもチェックするとよいでしょう。飛んでいる時は白いお腹と羽裏がよく目立ち、ハトやムクドリとははっきり違う飛翔スタイルなので、双眼鏡で見れば遠くからでも識別できます。餌をついばんでいない時は田んぼの畦に座ってじっとしていることも多いため、遠目には見つからなくても双眼鏡で畦沿いをくまなく探してみましょう。タゲリはケリよりひとまわり小さいですが、群れでいることが多いため発見は比較的容易です。冬の田んぼではケリと合わせて探してみると良いでしょう。
タヒバリ

タヒバリはセキレイ科に属する小鳥で、冬鳥として日本に渡来します。褐色がかった体に黒褐色の縦斑があり、一見地味ですが尾羽を上下に振る独特の仕草が目を引きます。名前が示す通り田んぼなどの見通しの良い場所を好み、地上をチョコチョコと歩き回りながらエサを探す姿がよく見られます。公園の芝生や河川敷、海岸の干潟など開けた環境にも生息しますが、田んぼで観察されることが特に多い野鳥です。タヒバリは小さな群れで行動することが多く、もし1羽だけ見つけても近くに仲間がいないか探してみると良いでしょう。収穫後の田畑では、地面でハクセキレイやカワラヒワなど他の小鳥と混じってエサをついばんでいる姿もよく観察されます。動いているときは目立ちますが、土色の体は田んぼでは保護色となり周囲に溶け込んでしまうため、気付かず近づいて飛ばしてしまうこともあります。しかし飛んでも近くの電線に止まって、しばらくするとまた地上に降りてくる習性があるので、一度飛ばしてしまっても慌てず周囲を探してみましょう。タヒバリは同じセキレイ科のハクセキレイやビンズイとシルエットが非常によく似ており、遠くにいる場合は見間違えやすいので、双眼鏡でしっかり確認することが大切です。
ホオアカ

ホオアカはホオジロ科に属する小鳥で、頬が赤褐色であることからこの和名があります。夏は高原の草原、冬は平地の草地や田んぼ周辺に生息する漂鳥で、日本では繁殖期と越冬期で生息場所が大きく異なります。夏の繁殖地ではノビタキと並んで高原を代表する野鳥で、草原から突き出た枝先や背の高い草の上にとまってさえずります。お気に入りのさえずり場所(ソングポスト)を見つけると、その場でじっくり観察できるでしょう。一方、冬のホオアカは河川敷や田んぼの畦付近の草むらに姿を潜めていることが多く、さえずらないため発見するのが非常に難しくなります。草の種子などを食べるホオアカは、冬にはセッカやオオジュリン(尾白鵐)などと同じ環境にいることが多いので、それらの野鳥が多い場所で合わせて探すと良いでしょう。冬の朝や夕方、草むらから飛び出して畦道に降り、ちょこちょこと採食する姿が見られることがありますので、双眼鏡で注意深く観察してみてください。ホオアカは留鳥ではないものの、一部は暖地で越冬する個体もいるため、地域によっては通年観察できる場合もあります。
ミヤマガラス

ミヤマガラスは冬にシベリア方面から飛来するカラス科の冬鳥で、日本では主に西日本~東日本各地の田園地帯で観察されます。ハシブトガラス(留鳥の大型のカラス)やハシボソガラスなど一般的なカラスに比べて一回り小さく、くちばしの付け根が白っぽく見えるのが見分けのポイントです。多くの場合数十羽以上の群れで行動し、田んぼのあぜや電線にずらりと群れで止まっている姿がよく見られます。ミヤマガラスを探す際は、見晴らしの良い場所から双眼鏡でカラスの群れを探すと良いでしょう。特に、川沿いや湖沼周辺の広大な田んぼでは堤防の上から広範囲を見渡せるため、大群を探すのに適しています。農耕地にミヤマガラスの大群がいると、その鳴き声や羽音でかなりの迫力があります。なお、ミヤマガラスの群れにはさらに小型のコクマルガラスが混じっていることが多く、群れにひときわ小さいカラスがいないか注意してみるのも面白いでしょう。夕方になるとねぐらに集結するため、日没前には次第に群れが上空を飛び交い騒がしくなる様子が見られます。かつてミヤマガラスは九州北部など限られた地域でしか見られませんでしたが、近年は分布が拡大し各地の田園で越冬する群れが確認されるようになっています。
カワラヒワ

カワラヒワはマヒワなどと同じアトリ科に属する小鳥で、留鳥または漂鳥として山地から平地まで幅広い環境に生息しています。緑がかった地味な体色ですが、翼にある鮮やかな黄色い斑(はん)が飛翔時によく目立ちます。スズメにやや似た体型・色合いですが、翼の黄色で区別できます。習性もスズメと共通点が多く、特に冬の田んぼではスズメとカワラヒワが大群を形成して一緒に地面で採餌したり電線に止まったりしている姿が見られます。カワラヒワは鳴き声が「キーコロコロ」という独特の囀りで、しばしば群れでさえずりながら飛び回ることがあります。冬の晴れた日には、刈り株だらけの田んぼに数十羽規模のカワラヒワの群れが舞い降り、落ちた穀物の粒や雑草の種子をついばむ様子が観察できます。用心深い鳥ではありますが、人里近くにも多いため比較的人間に馴れた個体もおり、公園などでは人の足元近くまで来ることもあります。春になると群れを解いて繁殖し、また秋に集まって越冬するというサイクルを繰り返します。
通年見られる野鳥
四季を通じて田んぼで観察できる留鳥(りゅうちょう)や周年生息種も数多く存在します。日本の田んぼ環境は、水稲農耕という人の営みと結び付いた特殊な生態系であり、一年中餌や棲みかを求めて居つく野鳥もいます。ここでは、季節に関係なく田んぼで見られる主な野鳥を紹介します。
アオサギ

アオサギは日本最大級のサギで、田んぼや河川、湖沼などに通年生息しています。青みがかった灰色の体色と黒い冠羽を持ち、くちばしは黄色で長く、じっと動かずに獲物を待つ姿はまるで水辺の仙人のようです。田んぼでは用水路やあぜの水たまりに入り、小魚やカエル、ドジョウなどを捕らえて食べます。留鳥として一年中見られ、繁殖も日本各地で行います。田んぼの中に悠然と立つ1羽のアオサギは大変目立ち、時折「ゴァー」と低く鳴く声が聞こえることもあります。夏には幼鳥が親とともに餌場に現れ、冬には単独または少数で行動します。アオサギは警戒心が強いようで実は人里の環境にも適応しており、都市近郊の田園でもよく見かけます。その存在感から田んぼの「主(ぬし)」とも言える存在で、他のサギ類(ダイサギやコサギなど)と一緒に群れていることもあります。
ダイサギとコサギ


田んぼで一年中見られる白鷺(しらさぎ)の仲間には、ダイサギとコサギがいます。いずれも全身が白いサギで、水田や用水路で魚やカエルを捕食する様子が通年観察できます。ダイサギ(留鳥として見られるのは主にチュウダイサギ)は大型の白鷺で、堂々とした体格が特徴です。非繁殖期は黄色いくちばしですが、繁殖期には口先が黒くなり、目先の皮膚は緑色に変化します。田んぼではゆっくりと歩き回り、大きなくちばしで素早く魚を捕らえます。コサギは小型の白鷺で、細身の体と黒いくちばし、そして足指が黄色いことが特徴です。活発に浅瀬を歩き回り、時には足で水底をかき回して獲物を追い出し、小魚やエビを捕まえて食べます。ダイサギとコサギはいずれも留鳥として全国で見られ、冬には水辺で一緒に餌を漁っている姿もしばしばです。夏の繁殖期には集団繁殖地(サギ山)でヒナを育て、そこから分散して各田んぼに飛来します。田んぼにスラリと立つ白鷺の姿は、日本の原風景として古くから親しまれており、その優美な立ち振る舞いは初心者にも観察しやすい野鳥です。
スズメ

スズメは言わずと知れた日本の身近な野鳥で、田んぼでも一年中見られる留鳥です。小さな鳥で、茶色い頭に黒い喉、淡い頬斑(ほおぶち)が特徴的な模様です。田んぼとの関わりも深く、稲作が始まって以来、人里の環境で繁栄してきた種でもあります。春から夏の繁殖期には茅葺(かやぶき)屋根や軒下、樹洞などに巣を作り子育てをしますが、田んぼ周辺でも巣材を集める姿が見られます。稲が実る秋には落ち穂を求めて大群が田んぼに押し寄せ、地表をちょんちょんと跳ね歩きながら籾(もみ)をついばみます。冬の間も群れで行動し、朝方にねぐらから出て日中は田畑で餌探し、夕方に再びねぐら(竹林や植え込み等)に帰る生活を送ります。スズメは人に最も身近な野鳥とはいえ、田んぼで観察すると自然の中で生き生きと動く野性の姿に改めて気付かされるでしょう。畦道に降りて餌を探す姿、仲間同士で毛づくろいする様子、群れが一斉に飛び立つ瞬間など、よく見ると興味深い行動がたくさん観察できます。なお、スズメの大群は時に稲に被害を与えることもあるため、農家にとっては悩みの種になることもありますが、日本の文化の中では古来より親しまれてきた存在でもあります。
ムクドリ

ムクドリも田んぼや農耕地で一年中見られる留鳥です。灰褐色の体にオレンジ色のくちばしと脚を持ち、頬が白いのが特徴です。農村から都市まで幅広い環境に適応しており、田んぼ周辺ではスズメと並んで普通に見られる野鳥です。ムクドリは地上を歩き回りながら昆虫やミミズを探し、口ばしで土をひっくり返して餌を捕ることもあります。春には夫婦で巣を作り、軒下や樹洞に巣ごもりしますが、繁殖期以外は大きな群れを作る習性があります。秋から冬にかけては、昼間に田畑でエサを探したムクドリたちが夕暮れ時になると塒(ねぐら)入り前に電線に集結し、ギャーギャーと騒々しく鳴き交わす光景が各地で見られます。田んぼでも昼下がりには数十羽の群れが降り立ち、落ち穂や地表の昆虫を盛んについばんでいます。人間に対する警戒心はそれほど強くなく、農道を人が歩いても数メートル先で採餌を続ける様子もしばしばです。夕方、大群で塒に帰る際には空を黒く染めるほどの規模になることもあり、自然の驚異を感じさせます。ムクドリは農耕地の害虫も大量に食べてくれる益鳥でもあり、田んぼの生態系の一翼を担う存在です。
ハクセキレイ

ハクセキレイは水辺や農耕地で一年中見られる白黒模様の野鳥で、田んぼでもおなじみです。頭から胸にかけて黒と白のはっきりした模様を持ち、長い尾を振りながらちょこまかと歩く姿が愛らしい鳥です。田んぼでは畦や用水路の縁を歩きながら水生昆虫や小さな生き物を捕食し、また地表の虫も積極的に追いかけます。春にはつがいで巣作りをし、家屋の屋根裏や土手の穴などで子育てをします。人里で暮らすため人への馴染みも深く、農作業中のトラクターの後を追いかけて掘り起こされた虫を狙う姿もしばしば観察されます。冬の田んぼではタヒバリと一緒に地面で採食する様子がよく見られるほか、収穫後の田畑に群がるスズメの群れに数羽のハクセキレイが混じっていることもあります。飛ぶときは細かく羽ばたきつつ波状に上下しながら飛ぶのが特徴で、「チチッ、チチッ」と甲高い地鳴きを発します。ハクセキレイの仲間にはセグロセキレイと呼ばれるものもおり、見た目はよく似ていますがセグロセキレイの方が背中が黒っぽく、より山間部の渓流などに多い傾向があります。いずれにせよ、水の流れる場所があれば年中姿を見ることができる野鳥であり、田んぼの用水路周りでも暇さえあれば尾を上下に振りつつ餌を探す姿が観察できるでしょう。
キジ

キジは日本の国鳥にも指定されている大型の鳥で、田んぼ周辺でも通年観察できる留鳥です。緑や紫に輝く羽色と赤い顔がとても美しい鳥です。メスは茶褐色で地味な体色をしており、草むらに隠れると見つけにくくなっています。キジは平地から山裾まで幅広く生息しますが、特に農耕地周辺でよく繁殖しています。春になるとオスが「ケーン、ケーン」という甲高い声で鳴き、羽ばたきながら縄張りを主張する姿が見られます。田んぼの畦や土手から突然バサバサッと飛び出すこともあり、その大きさに驚かされることもしばしばです。昼間は地上で木の実や昆虫を食べ、夕方になると藪や草地で休みます。手賀沼周辺の田んぼでもキジの生息密度は高く、春には親子連れの姿も観察されています。オスとメスが一緒にいる時は、オスがメスを守るように寄り添って移動する様子も見られます。秋から冬にかけては藪の中に潜んでいることが多いですが、餌を求めて農地に出てくることもあります。キジは人間にとっても馴染み深い鳥で、民話や文学にも登場します。田んぼ周辺で「ケーン!」という鳴き声が聞こえたら、周囲の畦や草地を注意深く探してみてください。美しい雄のキジが姿を現すかもしれません。
野鳥観察のコツとマナー
田んぼでの野鳥観察をより楽しむために、いくつかのコツとマナーを押さえておきましょう。
- 遠くから静かに観察する: 田んぼの野鳥は意外と警戒心が強いものです。近づきすぎるとパッと飛び立ってしまうことがあります。双眼鏡やフィールドスコープ(望遠鏡)を活用し、できるだけ野鳥との距離を保って観察しましょう。特に冬は隠れる草木が少ないため、人影に敏感になります。鳥が落ち着いて採餌・休息できる距離をとることが大切です。
- 注意深く探す: 広い田んぼでは、ただ何となく眺めているだけでは見落としてしまう野鳥がたくさんいます。必ず立ち止まって双眼鏡で田んぼ全体を見渡すようにしましょう。タシギなどの保護色の鳥は止まっていると本当に見つかりませんが、「いない」と決めつけずにじっくりチェックすることが発見のコツです。また、目に入った1羽だけで満足せず、その近くに仲間が潜んでいないかも探しましょう。群れで生活する鳥は1羽見つかれば他にもいる可能性が高いです。
- 鳥の行動を利用する: 野鳥それぞれの習性を知っておくと観察の助けになります。例えばケリは猛禽類が接近すると大きな声で鳴きながら群れで飛び立つため、遠くでケリの鳴き声が聞こえたり一斉に飛び立つ様子を見たら双眼鏡でその方向の田んぼを探すと居場所が分かります。ムナグロのように飛んでいる群れがいたら着地地点を探す、タヒバリのように飛び立っても近くの電線に止まる習性がある鳥は一度飛んでも諦めず探す、といった具合です。鳥の行動パターンを利用して効率よく観察しましょう。
- 季節と時間帯を選ぶ: 本記事で紹介したとおり、季節によって見られる鳥は変化します。お目当ての鳥がいる場合、その鳥が飛来・繁殖する季節に合わせて田んぼに出かけましょう。例えばタマシギなら春~夏の早朝、タゲリなら冬の夕方などが狙い目です。また、一般に野鳥は朝と夕方に活動が活発になるため、早朝から午前中に探鳥すると出会える確率が高まります。逆に夏の炎天下の昼間などは鳥の動きも鈍くなるため、休耕田の水辺など涼しい場所を重点的に探すと良いでしょう。
- マナーを守る: 野鳥も私たちと同じ自然の一部であり、安心して暮らせる環境を守ることが大切です。田んぼは農家の方の私有地である場合がほとんどなので、無断で立ち入らないようにしましょう。畦道は農作業の大切な通路です。見学の際は邪魔にならないよう配慮し、車で行く場合も農道に勝手に駐車しないよう注意します。大人数で観察するときは私語や足音にも気を付け、静かに行動してください。珍しい鳥が出た場合でも、追い回したり大声を出したりしないことがマナーの基本です。野鳥にストレスを与えない距離を保ち、観察に夢中で田んぼの用水路や泥にはまって怪我をしないよう自身の安全にも留意しましょう。写真撮影する際もフラッシュは使わず、三脚は通行の邪魔にならない場所で使用します。他のバードウォッチャーがいる場合はお互いに譲り合い、気持ちよく観察を楽しめるように心がけましょう。
田んぼで見られる野鳥の魅力まとめ
四季折々に多種多様な野鳥が集う日本の田んぼは、初心者からベテランまで楽しめる絶好の探鳥フィールドです。春は旅鳥や夏鳥との出会い、夏は繁殖のドラマ、秋は収穫の恵みに群れる鳥たち、冬は厳しい寒さの中で逞しく生きる鳥たち──田んぼを訪れる野鳥の顔ぶれは季節ごとに大きく変化し、そのたびに新鮮な驚きがあります。一年を通してケリやサギ類が居ついているおかげで、いつ訪れても何かしらの野鳥に出会えるのも田んぼの魅力です。また、開けた田園風景の中では野鳥を比較的探しやすく、動きも観察しやすいので、バードウォッチング初心者にとっても格好の入門環境と言えるでしょう。
さらに、田んぼは人と野鳥の共生の場でもあります。農作業の合間にトラクターの後をついてくるハクセキレイやムクドリ、日暮れにねぐら入りするスズメやムクドリの大群、害虫をついばんで稲を守ってくれるサギたち。日本の里山の原風景には、いつも野鳥たちの姿がありました。現代でも探鳥地として整備された大きな公園や保護区だけでなく、身近な田んぼに目を向ければ豊かな生態系が息づいていることに気付かされます。
ぜひ季節ごとの田んぼに足を運び、今回紹介した野鳥たちを探してみてください。双眼鏡片手に野鳥の姿を見つけた時の喜びや、美しい声を耳にした時の感動は何ものにも代えがたい体験です。朝霧にけむる春の田園、青空の下でヒバリが舞う夏の畦道、夕日に染まる秋の刈田、透き通る冬空の下で羽ばたく群れ…。日本の田んぼには、野鳥たちが織りなすドラマと魅力が一年中詰まっています。その恵み豊かなフィールドで、自然と野鳥の素晴らしさを存分に味わってください。

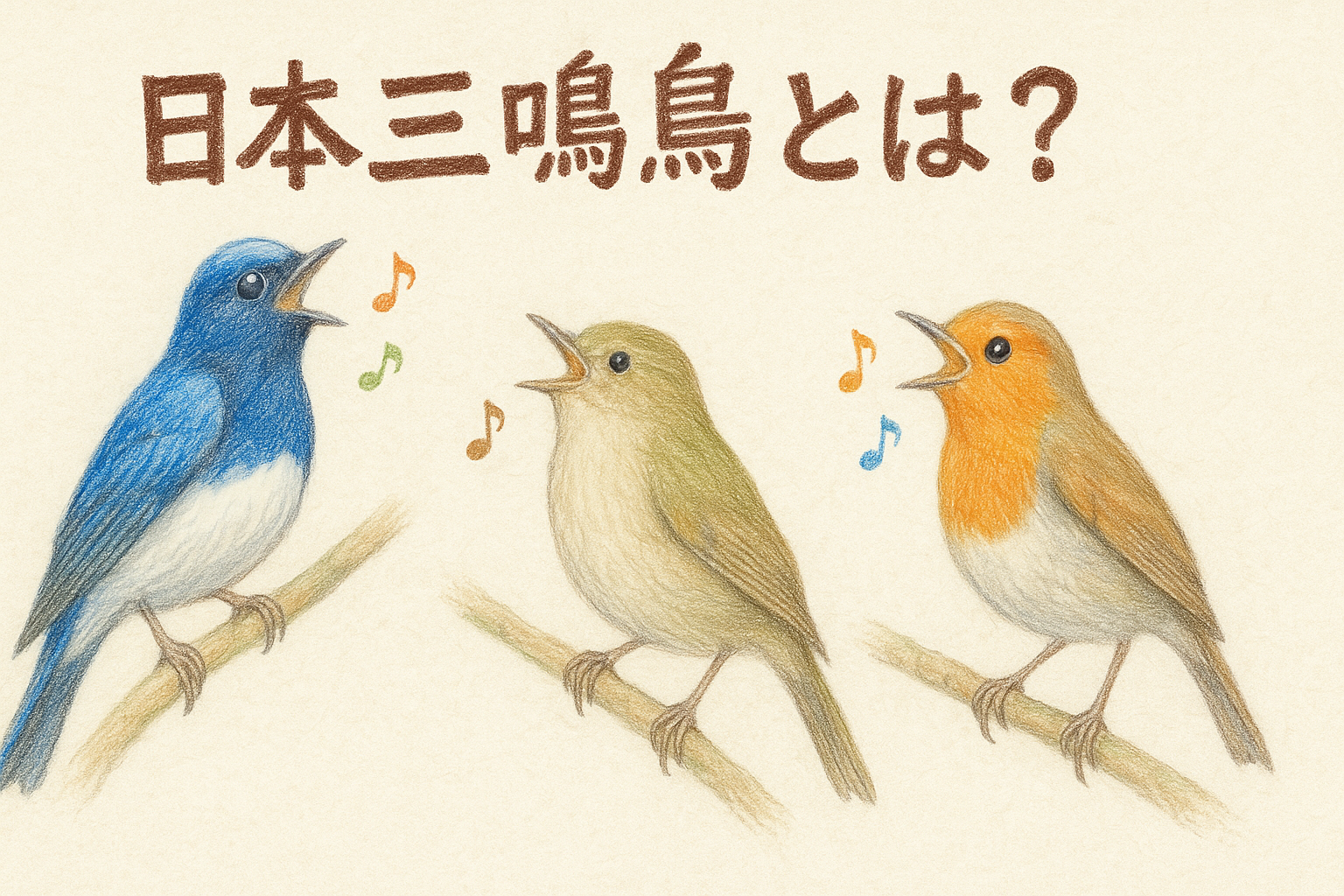
コメント