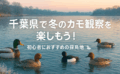日本には、真っ白な羽を持つ美しい野鳥が数多くいます。中でも川や田んぼで見られる白いサギ類は、まとめて「シラサギ」と呼ばれることもありますが、実は「シラサギ」という種類の鳥はいません。シラサギとはダイサギ・チュウサギ・コサギなど白いサギ類の総称で、ぱっと見はよく似ていますが、大きさやくちばし・足の色に違いがあります。今回は、そんな日本で見られる代表的な「白い鳥」たちを親しみやすい口調で紹介します。水辺でひときわ目立つ白いサギや、冬の風物詩である白鳥、そして少し珍しい白い鳥たちについて、それぞれの特徴や生態、観察のポイントなどを詳しく見ていきましょう。
コサギ

コサギは全身が白い小型のサギで、田んぼや川沿い、池など水辺ならほとんどどこでも見られるといっていいほどポピュラーな存在です。くちばしは一年中黒く、足も黒ですが足指だけが黄色いのが最大の特徴で、この黄色いスリッパを履いたような足がコサギを見分ける決定的なポイントになります。繁殖期には後頭部に細くて長い白い冠羽(かんむりばね)が2本伸び、背中にも飾り羽が現れてとても優美です。こうした冠羽や飾り羽は繁殖期だけなので、春から初夏にかけてコサギを見るときは注目してみましょう。
生息地と分布:コサギは日本全国に留鳥として分布し、都市部から農村部まで幅広い水辺の環境で一年中観察できます。川沿いの遊歩道や公園の池、水田などで小魚やカエルなどを狙って浅瀬を歩き回る姿がよく見られます。人里にも適応しており、都会の川でも水辺を覗き込むと意外とコサギがいるものです。全身真っ白で目立つうえ群れで行動することも多いため、その姿を見つけるのは難しくありません。夕方、水辺に白い鳥が集まっているときは、コサギの集団がねぐら入りしている可能性があります。
観察のポイント:コサギは警戒心がそれほど強くないので、公園の池などでも比較的近くで観察できます。獲物を探すときは水辺を小走りに動き回ったり、足先を震わせて小魚を追い出したりするユニークな行動も見せます。コサギだけで群れを作ることもありますが、しばしば他の白いサギ類(ダイサギやチュウサギ)と混ざって3種類のシラサギが一緒に行動していることもあります。そんな時はぜひ大きさやくちばし・足の色の違いに注目してみてください。コサギは他の2種に比べて体が小さく足指が黄色いので、一目見分けられるようになると探鳥がさらに楽しくなるでしょう。
チュウサギ

チュウサギはコサギより一回り大きく、ダイサギよりは小さい中型の白いサギです。その名のとおりサイズは「中くらい」ですが、野外で見分ける際はサイズ感だけでなくくちばしや足の色の違いも参考になります。パッと見はダイサギによく似ていますが、チュウサギのくちばしはダイサギほど長くなく、足も含めて全体にややスマートな印象です(※ダイサギとの詳しい識別点は後述します)。コサギと違って足指まで黒いため、群れでいる時はコサギの黄色い足指と比べて見分けることができます。
生息地と分布:チュウサギは日本では数が減少傾向にありますが、夏に本州以南の水田地帯に飛来する夏鳥として知られています。普段は留鳥のダイサギ・コサギがいる田んぼにも、夏になるとチュウサギとアマサギが加わることがあります。特に水田で繁殖するため、初夏の田植えシーズンには田んぼでエサをとる姿が観察されます。また、コロニー(集団繁殖地)では他のサギ類と混ざって巣作りをするため、コサギやダイサギのコロニーにチュウサギが紛れていないか探してみるのもよいでしょう。
観察のポイント:チュウサギは夏の間に日本にやって来る白サギです。観察しやすい時期はやはり夏で、水田地帯が狙い目です。コサギやアマサギの群れの中に混じっていることも多いので、小~中型のサギが田んぼに集まっていたら注意して探してみましょう。コサギ(全長約60cm)より大きく、ダイサギ(全長約90cm)より小さいので、何羽も集まっている場合はチュウサギの大きさが目安になります。また、繁殖期にはチュウサギは虹彩が赤く、口元が黄色になり、胸にもふわふわとした飾り羽が現れます。他のシラサギにはない独特の装いなので、運が良ければそうした姿を見ることができるかもしれません。
類似種との見分け方:ダイサギとの区別が難しい種類ですが、フィールドではチュウサギの方が首がやや短く太い印象を受けることがあります。このように体のパーツに注目すると識別しやすいでしょう(ただし個体差もあるため要注意です)。いずれにせよ、チュウサギとダイサギが並んでいると体の大きさの違いが明らかなので、できれば複数の個体を比較して見分けると確実です。
ダイサギ

ダイサギは白いサギ類の中では最も大きな種類(全長約90cm)で、その堂々とした姿から「大サギ」の名が付いています。首も脚も長く、遠目にも優雅に映える野鳥です。水辺でジッと獲物を狙う立ち姿は風格さえ感じられ、白い羽が日差しに輝く様子はとても絵になります。日本では留鳥または渡り鳥として各地で見られ、一年を通して川や湖沼、水田などあらゆる水辺に生息しています。特に冬になると北から渡ってきた個体が加わり個体数が増えるため、白いサギが目立つ季節です。
生息地と分布:ダイサギは全国各地の水辺で観察できます。都市近郊の川から農村の田んぼ、湖のほとりまで、幅広い環境に適応しています。主に魚やカエル、小型の哺乳類などを餌にするため、水があればどこへでも姿を現します。留鳥としてそのまま居着いている個体も多く、東京など都市部でも一年中見かけますが、寒い地域の個体は冬に暖地へ渡るものもいます(ダイサギは複数の亜種があり、日本では留鳥のチュウダイサギと冬鳥のオオダイサギがいるとされます)。いずれにせよ、冬の水辺ではダイサギとコサギが並んでいる光景が普通に見られ、「白いサギ=ダイサギかコサギ」というくらい出会う頻度の高い鳥です。
観察のポイント:ダイサギは警戒心が比較的強く、人が近づきすぎると優雅に飛び去ってしまいます。観察するときは双眼鏡などを使って距離を保つと良いでしょう。群れで行動することも多く、5~6羽のダイサギが田んぼに点在してエサをとっていることもあります。また、繁殖期(春~夏)には集団繁殖地でコロニーを形成し、コサギやゴイサギと一緒に集まって巣づくり・子育てをします。コロニーでは多数のサギ類が間近で見られる絶好の機会ですが、繁殖期の鳥たちはデリケートなので遠くから静かに見守りましょう。
類似種との見分け方:チュウサギとの違いでも触れましたが、ダイサギはチュウサギより明らかに大型です。複数羽がいれば大きさで判別できますが、1羽だけだと判断が難しいこともあります。その場合はくちばしの色に注目しましょう。ダイサギのくちばしは、夏(繁殖期)には黒くなり、冬には黄色になる傾向があります。一方、チュウサギは繁殖期でもくちばし全体が真っ黒になることは少なく、基部が黄色を帯びます。またダイサギの目先(目とくちばしの間)は繁殖期に鮮やかな青緑色になり、これもチュウサギには見られない特徴です。足については、ダイサギ・チュウサギともに足全体が黒く足指も黒いので、足指が黄色いコサギとは容易に区別できます。
アマサギ

アマサギは他のシラサギと少し趣が異なるサギです。夏鳥として毎年春から初夏に日本に渡来し、主に水田や湿地で見られます。一番の特徴は羽色が季節によって変化することで、夏の繁殖期には頭や首、背中が名前の由来にもなっている亜麻色(薄いオレンジ色)に染まります。

白いサギが多い中で、黄金色にも見えるアマサギの夏羽はひときわ目立ち、「田んぼの花」と称されるほどです。一方、冬羽(非繁殖期)は全身が真っ白になるため、見た目はコサギやチュウサギとよく似ています。そのため白い冬のアマサギを観察する際は、他のシラサギと混同しないよう注意が必要です。
生息地と分布:アマサギは春から夏にかけて日本にやって来る夏鳥で、本州以南の広い田園地帯で見ることができます。特に水牛がいる田んぼなどでは、牛の背中に乗って虫を捕る姿が海外で知られていますが、日本では主に水田で稲についている害虫やカエルなどを捕食します。繁殖期にはダイサギやコサギなどと混じって集団繁殖地(サギ山)でコロニーを作り子育てします。日本では主に九州から本州にかけて繁殖し、冬になると東南アジア方面へ渡っていく個体が多いとされています。
観察しやすい時期・場所:夏に亜麻色の婚姻衣をまとったアマサギを見たい場合は6月頃がもっともおすすめです。ちょうど繁殖が軌道に乗り、雄がきれいな飾り羽と婚姻色を見せてくれる頃合いです。逆に真っ白な冬羽のアマサギを見たい場合は、繁殖を終えて南に帰る直前の初秋(9月頃)がねらい目です。観察ポイントとしては、広い田んぼを上から見渡せる場所が良いでしょう。アマサギは群れで行動していることが多いので、土手や堤防などに立ってあたりの田んぼを双眼鏡で探すと見つけやすいです。ただし、稲が生長して背丈ほどに伸びてしまうと小柄なアマサギは稲に隠れて見つけにくくなるため、田植え直後で稲が低い5月頃のほうが観察しやすいでしょう。
その他の豆知識:アマサギはコサギよりも体が小さいため、普段見慣れたサギたちよりもひと回り小さな白いサギの群れを見つけたら要チェックです。また、繁殖期には目先(目の周り)やくちばしが赤く染まる婚姻色が現れることでも知られます。赤みを帯びた顔に亜麻色の羽という派手な装いはこの時期だけなので、一度見ると印象に残るでしょう。アマサギの亜麻色は夏が過ぎるとすぐに白く抜けてしまいますが、そんな季節ごとの変化もアマサギ観察の楽しみのひとつです。
クロサギ(白色型)

クロサギは本来、真っ黒な体色が名前の由来ですが、沖縄などでは全身が真っ白な「白色型」も観察できます。黒色型と白色型が同じ岩場で並ぶこともあり、そのコントラストはまさに自然の不思議を感じさせてくれます。白色型は遠目にはコサギと紛らわしいものの、クロサギは海沿いの岩場という独特の環境を好むため、内陸の水田や川辺で見られるコサギとは生息場所で区別できます。沖縄の豊崎干潟や来間大橋周辺などでは、黒色型と白色型が一緒に磯を歩き回る姿が度々報告されています。米須海岸では「真っ白なクロサギ」をコサギと見間違えないよう注意喚起されており、白いサギを見つけたときはまず海岸か内陸かを確認すると間違いが減ります。動かずに岩と同化していることも多く、見つけにくいのも特徴です。
生息地と分布:クロサギは留鳥または漂鳥として海岸沿いの岩場に定着しており、干潮時に岩礁が広く現れる場所で探すのがコツです。白色型は黒色型より分布が狭く、主に沖縄や宮古島など南西諸島で見られます。本州では黒色型が中心ですが、神奈川県の城ヶ島・江の島、千葉県の君ヶ浜しおさい公園などでは稀に白色型が混じる可能性もあります。
観察のポイント:探鳥は干潮前後に岩場が露出するタイミングが最適で、磯の上をゆっくり歩きながら小魚を狙う姿が見られます。白色型は背景と溶け込む黒色型に比べてかえって目立つため、遠くからでも見つけやすい半面、コサギとの誤認に注意が必要です。潮だまりを入念にチェックし、動きの少ない個体は双眼鏡でじっくり観察しましょう—ときに白と黒が並んで採餌する貴重なシーンに出会えます。岩場は滑りやすく、波しぶきがかかることも多いので、クロサギ観察の際は足元と潮位に十分注意してください。
ヘラサギ

ヘラサギはその名のとおり、先がヘラ状に平たい独特なくちばしを持つ大型の水鳥です。サギ科に近いトキ科の仲間で、体は全身が白色です。一見するとダイサギなどの大きな白サギに似ていますが、首が太く全体的にがっしりした体つきで、普通のサギより重厚な印象を受けます。飛ぶときは首を前にまっすぐ伸ばして飛ぶ点もサギ類との違いです(サギは飛翔時に首をS字にたたみます)。日本では個体数がとても少なく、主に冬鳥として河口や干潟などに渡来する稀少種です。
生息地と観察時期:ヘラサギは冬の時期に、日本各地でもわずかな場所でしか観察例がありません。有名なのは東京の葛西臨海公園や、新潟の福島潟、沖縄の漫湖(まんこ)などで、これらはいずれも干潟や浅い池がある水辺環境です。ヘラサギは首を左右に振りながら浅瀬を歩き、ヘラ状のくちばしで水をかき回して餌を探すというユニークな採餌行動をとります。この「くちばしを振り子のように振る」仕草は遠目にも目立つので、干潟で何か白い鳥が首を振っていたらヘラサギかもしれません。日本に飛来する数は非常に少ないため、出会えたらとてもラッキーな鳥です。
観察のポイント:ヘラサギは世界的にも希少な鳥で、日本に来る個体数もごくわずかです。そのため、探す際はまずヘラサギの飛来記録がある場所に出向くのが近道です。ヘラサギは姿形がよく似たクロツラヘラサギ(後述)と一緒に行動していることが多いため、クロツラヘラサギが越冬している干潟を中心に探すと見つかる可能性が高まります。実際、葛西臨海公園でもまずクロツラヘラサギの群れが越冬し、そこにヘラサギが1羽だけ混じっているケースが見られます。識別ポイントは顔の色で、ヘラサギは目の周りの皮膚が白色(淡色)なのに対し、クロツラヘラサギは名前のとおり顔が真っ黒な点が異なります。遠くからだと違いが分かりにくいこともありますが、双眼鏡や望遠鏡でぜひ顔の色を確認してみてください。
クロツラヘラサギ

クロツラヘラサギは、ヘラサギの仲間ですが顔が黒いことが大きな特徴です。くちばしも黒いため、一見すると顔からくちばしまで真っ黒で、白い体とのコントラストがはっきりしています。世界的に見ても生息数が非常に少ない絶滅危惧種で、日本に飛来する数も限られています。主に冬鳥として沖縄や九州に少数が越冬しにやって来ますが、まれに本州でも観察されることがあります。
生態と行動:クロツラヘラサギもヘラサギ同様に河口の干潟や浅い池を好み、大きなヘラ状のくちばしで水中の小魚や甲殻類を探して食べます。数羽から十数羽程度の小さな群れを作って行動することが多く、たまにヘラサギも混じって一緒に餌を探していることがあります。干潟では潮が引いたタイミングで活発に採餌し、満潮時には近くの浅瀬や中州で群れで休息します。休んでいる時はくちばしを体にうずめてじっとしていますが、その状態だとダイサギなどの普通のサギと紛らわしく、判別が難しいことがあります。遠くで白いサギが首をすくめて休んでいるのを見つけたら、双眼鏡で顔が黒くないか確認してみましょう。もし顔が真っ黒なら、それはクロツラヘラサギです!
観察のポイント:クロツラヘラサギは日本では特定の限られた場所でしか見られません。有名な越冬地の一つが沖縄本島の漫湖で、毎年冬になると数十羽規模の群れが飛来します。漫湖では干潮時に干潟が広がりすぎて鳥が遠くに散らばるため、干潟が出始める頃合い(干潮から満潮に向かうタイミング)を狙っていくと良いとされています。また、漫湖以外では近隣の三角池や豊崎干潟にも分散することがあるため、漫湖で見つからない場合はこれら周辺もチェックすると見つかるかもしれません。いずれにしても数が少ない鳥なので、地元の野鳥情報(観察センターの掲示板やスタッフブログ)を確認してから出かけるのがおすすめです。
豆知識:クロツラヘラサギは繁殖地の中国や韓国でも保護活動が進められている希少種です。一時は世界で200羽以下とまで減少しましたが、近年は保護の甲斐あって少しずつ個体数が回復しつつあります。それでも日本で見られるのはせいぜい数十羽規模。見られたら本当に幸運な「幸せの白い鳥」と言えるでしょう。
コハクチョウ

コハクチョウ(小白鳥)は、冬になると日本にやって来る大型の水鳥です。全身純白の体にオレンジ色と黒の模様が入った大きなくちばしを持ち、湖沼や河川、そして日中は餌を求めて周囲の田んぼにも繰り出します。ハクチョウの仲間の中では体がやや小さく(それでも翼を広げると2メートルほどあります)、首も細めですが、それでも野鳥の中では最大級のサイズです。真っ白な体は遠くからでもよく目立ち、群れでいることが多いため、生息地で見つけるのはそれほど難しくありません。実際、場所によっては何千羽もの大群が越冬に訪れることもあります。
生息地と観察時期:コハクチョウは冬鳥として北海道から本州、九州まで飛来します。特に本州日本海側の湖沼や、関東以北の水辺に多く越冬します。代表的な飛来地として、新潟県の瓢湖(ひょうこ)や福島潟、福島県の猪苗代湖、宮城県の伊豆沼・内沼、関東では千葉県本埜(もとの)白鳥の郷などが有名です。こうした場所では毎年定期的にハクチョウの群れが飛来し、昼間は近隣の田んぼで餌を食み、早朝や夕方になると水辺に帰ってきて休むというパターンが多く見られます。そのため昼間に訪れても肝心のハクチョウがあまりいないこともありますので(田んぼに出払っているため)、朝夕の時間帯を狙って行くといいでしょう。夕暮れ時、水面に次々とハクチョウが舞い降りてくる光景はとても感動的です。
類似種との見分け方:コハクチョウは後述するオオハクチョウ(大白鳥)と見た目が非常によく似ています。一緒に行動していることも多いので、飛来地では両者が混じった群れになっているのが普通です。見分けるポイントはいくつかありますが、最もわかりやすいのはくちばしの黄色い部分の大きさです。一般にオオハクチョウは黄色い部分が大きくて口角(くちばしの付け根の切れ込み)が目の後方まで達し、黄色と黒の境目が尖るのに対し、コハクチョウは黄色い部分が小さく、境目の形も丸みを帯びる傾向があります。パッと見では難しいかもしれませんが、近くで写真を撮って拡大してみると違いが分かることもあります。また、オオハクチョウの方が体が一回り大きいので、群れの中にいる場合はその大きさで目立ちます。実際、群馬県の多々良沼では飛来するハクチョウの大半がコハクチョウでオオハクチョウは少数派ですが、体の大きいオオハクチョウはコハクチョウの群れに混じるとよく目立つため、大きさを頼りに探すと良いとされています。
豆知識:コハクチョウの群れの中には、まれに「アメリカコハクチョウ」と呼ばれる亜種(北米産のコハクチョウ)が紛れていることがあります。アメリカコハクチョウはくちばしの黄色い部分がごく僅か(ほとんど黒い)である点以外はコハクチョウと瓜二つですが、日本にもごくたまに飛来することが知られています。ハクチョウの飛来地で観察する際は、くちばしの模様に注目して珍客を探してみるのも一興です。なお、幼鳥は全身が灰褐色を帯びていますが、群れで行動して親について回るのですぐに分かるでしょう。
オオハクチョウ

オオハクチョウ(大白鳥)はコハクチョウと並ぶ日本の冬の代表的な白鳥です。体長約140cmにも達する大型の水鳥で、国内で見られる野鳥の中では最重量級ともいわれます(体重は10kg前後にもなります)。白鳥というと優雅なイメージがありますが、オオハクチョウは「クォー、クォー」と大きな声で鳴くことでも知られ、群れで鳴き交わす声は遠くからでもよく響きます。基本的な生活パターンはコハクチョウと同じで、昼間は田んぼなどで採食し、朝晩に水辺で休むことが多いです。
生息地と観察ポイント:オオハクチョウもコハクチョウ同様に冬鳥として北海道から本州に飛来し、湖や沼で越冬します。東北・北海道での比率が高く、関東以南では飛来数が少なめですが、それでも千葉県本埜白鳥の郷など毎冬見られる場所があります。コハクチョウと一緒に行動していることが多いため、一つの飛来地で両方の種が混ざっているケースがほとんどです。そのため観察の際は識別に注意が必要ですが、前述のとおり群れの中では体の大きなオオハクチョウが目立つので、大きい個体を探せば見つけられるでしょう。たとえば群馬県館林市の多々良沼では飛来する白鳥の大半がコハクチョウですが、少数いるオオハクチョウはそのサイズの差で発見できます。また、白鳥の飛来地では朝夕に多くの個体が戻ってくるため、平日の早朝など人出の少ない時間帯に行くと落ち着いて観察できます。
オオハクチョウならではの話題:オオハクチョウはユーラシア大陸北部のツンドラ地帯で繁殖し、数千キロの旅を経て日本にやって来ます。毎年同じ家族・群れで同じ場所に飛来する傾向があり、長年白鳥を観察している人の中には「○○湖の○○号」と個体識別して見守っている方もいます。また、日本では基本的に冬にしか見られませんが、中には怪我や体力不足で北へ帰れずに夏を越す個体もごく一部います。冬以外の季節に偶然白鳥を見かけたら、それは何らかの理由で渡りを断念したオオハクチョウやコハクチョウかもしれません。
コブハクチョウ

コブハクチョウは、公園の池などでおなじみの外来種の白鳥です。ヨーロッパ原産の種で、本来は日本に生息していませんが、観賞用に各地で飼育されていたものが逃げ出して定着しました。現在では全国の湖沼や公園で半野生化した個体を見ることができ、通年観察可能な白鳥として知られます。真っ白な体にオレンジ色のくちばし、そして額に黒いコブ(瘤)を持つ姿はとても印象的で、英名の“Mute Swan”が示すように他の白鳥に比べて鳴き声が静かなことも特徴です。
生息地と生活:コブハクチョウは人里の池や湖によく適応しており、都心の公園から自然度の高い湖まで幅広い環境に生息します。多くは人為的に放されたものの子孫であるため、渡りをせず一年中同じ場所に留まります。そのため冬だけでなく夏でも白鳥が見られる場合、それはコブハクチョウである可能性が高いです。東京近郊では手賀沼(千葉県)や井の頭公園(東京都)の池などに定着個体が知られています。草食性が強く、水草や陸生植物の葉などを食べて暮らしており、人から餌付けされている個体も少なくありません。
見分け方と豆知識:オオハクチョウやコハクチョウと比べると、コブハクチョウはまずくちばしの色で判別できます。鼻筋に黒いコブがあり、くちばし全体が黄色ではなく赤橙色を帯びているのが最大の特徴です。また、先述の2種と違い季節移動をしないため、冬以外の季節にも成鳥・幼鳥ともに見られます。体の大きさはオオハクチョウとほぼ同じで(どちらも全長約150cm前後)、コハクチョウよりは明らかに大きいため、並んだ際の迫力は他の白鳥に引けを取りません。なお、コブハクチョウはつがいの絆が強く、繁殖期以外でもオスとメスが寄り添って泳いでいる姿をよく見かけます。優雅に首を曲げて泳ぐペアの姿は、まさに絵に描いたような「白鳥の湖」の世界です。
シロカモメ

シロカモメは、その名のとおり体が白っぽいカモメで、冬の海辺に飛来します。カモメ類の中でも翼の先まで真っ白(または淡いグレー)で、成鳥では黒い羽がほとんど無いため、一見すると純白のカモメに見えます。北海道や東北地方などの北日本の沿岸で見られるほか、寒い時期には関東以南の港にも稀に姿を現します。体長は60cmほどあり、大型のカモメ類に属しますが、同じく大きいオオセグロカモメなどと比べると翼の先に黒が入らないぶん柔らかな印象を受けます。
生息地と観察時期:シロカモメは冬鳥として日本に飛来し、主に港湾や河口、漁港周辺で見られます。数は多くなく、大半の群れはもっと北の地域(ベーリング海沿岸など)で越冬するため、日本では各地で数羽程度が散見されるレアな存在です。関東では銚子漁港(千葉県)や波崎新港(茨城県)などで記録があり、茨城県の波崎では若鳥が地元のカモメの群れに混ざって餌をあさっている姿が観察されています。シロカモメは他のカモメ類と行動を共にすることが多く、ウミネコやセグロカモメの大群の中に1羽だけ混じっているという状況もしばしばです。そのため、大きなカモメの群れを見る機会があれば、黒い羽の少ない真っ白な個体がいないか探してみると良いでしょう。
観察のポイント:シロカモメを探すコツは、やはりカモメ類の大群を一羽一羽よく観察することです。銚子漁港の一の島防波堤などはカモメ類の識別練習に最適なスポットで、セグロカモメやウミネコに混じってミツユビカモメやシロカモメなどの珍しいカモメが紛れている可能性があります。実際に銚子で観察された例では、シロカモメが堤防で他のカモメと一緒に休んでおり、頭を背中に突っ込んで眠っていました。ぱっと見見逃してしまいそうでしたが、白い羽が他のカモメよりも明るく目立つため、「あれは何だろう?」と双眼鏡で確認してシロカモメと分かったそうです。シロカモメの幼鳥(第一冬羽)は全身淡い茶色がかった白で、成鳥になるとより純白に近づきます。出会えれば観察しがいのある魅力的な白い鳥です。
最後に
白い野鳥たちは、水辺の風景や冬の空気によく映え、見る者の心を惹きつけます。「白い鳥を見たい!」と思ったら、ぜひ今回紹介したポイントを参考に探してみてください。コサギたちが舞う初夏の田んぼ、白鳥の優雅な飛来する湖沼、そして運が良ければ出会える珍しい白い鳥たち…。フィールドで実際に観察すれば、その美しさとたくましさにきっと感動することでしょう。皆さんも双眼鏡を片手に、幸運の白い鳥たちとの出会いを楽しんでくださいね。